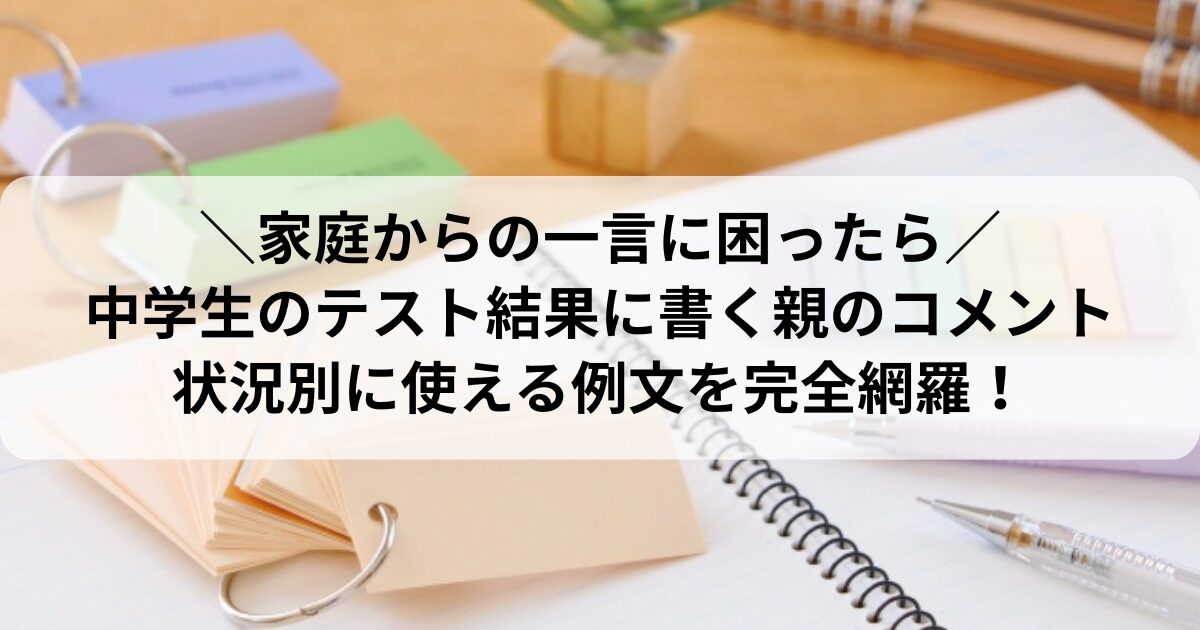「成績表の“家庭からのコメント欄”、毎回何を書いたらいいか迷ってしまう…」そんな保護者の方、多いのではないでしょうか。
点数が良かったときも、思うようにいかなかったときも、中学生の子どもにとって親の言葉は大きな力になります。
でも、“どう伝えたらいいのか”が難しいですよね。
この記事では、そんなお悩みをまるごと解決!
成績別・状況別に使える、中学生のテスト結果に親が書く具体的なコメント例文を80パターンご紹介します。

「伝えたいけど、うまく書けない」そんなあなたの言葉探しに、きっと役立つはずです。
成績表の「家庭からのコメント欄」の書き方や例文80選


成績表の「家庭からのコメント欄」の書き方や例文を詳しくご紹介します。
「家庭からのコメント欄って、毎回なにを書いたらいいのか迷う…」という声、多いんです。



でも、ちょっとしたコツを知っておくだけで、ぐっと書きやすくなりますよ!
まずは努力や姿勢をしっかり褒める
親のコメント欄の冒頭で必ず入れたいのが、「子どもの努力や変化に対する肯定的な言葉」です。
テストの点に関わらず、「毎日机に向かっている姿を見ていました」「苦手な英語に取り組もうとする姿勢が見られました」など、親から見た“日々の様子”を伝えるのが効果的です。
先生にとっても、「家庭でも見守っている」と感じてもらえる内容になるんです。
たとえ結果が伴っていなくても、プロセスを褒めることで子どものモチベーションにもつながります。
改善点は前向きに、やんわり書く
「成績が下がった」「提出物が遅れがちだった」など、改善点を伝えたいときは、できるだけやんわり、前向きな言葉を使いましょう。
たとえば、
- 「漢字の書き取りがやや苦手なようなので、家庭でも声かけをしていきたいです」
- 「数学の復習を意識して取り組めるよう、環境づくりをしていきます」
など、“できていない”を指摘するのではなく、“これから支えていく”姿勢が大切です。
否定的な文面よりも、協力的な印象を与えた方が先生との信頼関係も築きやすくなりますよ。
先生への感謝や家庭のサポート意欲を表す
最後に締める文として、先生への感謝や家庭での関わりを示す一言を加えると、印象がとても良くなります。
たとえば、
- 「今後ともご指導のほど、よろしくお願いいたします」
- 「引き続き、家庭でも見守ってまいります」
- 「本人ともよく話し合い、意欲を引き出していきたいと考えております」
など、親としてのスタンスを表すと、先生との連携がスムーズになります。
“家庭と学校はチーム”という意識を持つと書きやすくなりますよ。
実際に使える親のコメント例文80選【点数別・性格別】



以下に、「家庭からのコメント欄」にそのまま書ける例文を点数別・状況別にまとめました。
- 点数が高かったときのコメント例文8選
- 平均点くらいだったときのコメント例文8選
- 点数が低かったときのコメント例文8選
- マイペース・内向的な子のコメント例文8選
- 頑張っているが結果が出ない場合のコメント例文8選
- 成績が安定してきた子のコメント例文8選
- 苦手な教科への意識が高まった子のコメント例文8選
- 反省を次に活かそうとしている子のコメント例文8選
- 目標設定や学習計画に意欲を見せ始めた子のコメント例文8選
- 高校受験を控えた中学3年生へのコメント例文8選
テストの結果で点数が高かったときの親のコメント例文8選
テストで高得点を取ったときは、努力が実ったことを一緒に喜び、しっかりと認めてあげることが大切です。
ただ「すごいね!」だけで終わるのではなく、どのような努力があったのかに触れることで、子どもはさらに自信をつけていきます。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 本人の努力が結果につながり、自信を深めている様子が見られました。次回も継続できるよう励ましてまいります。 |
| 苦手意識のあった教科で高得点を取ることができ、自信につながっている様子です。引き続き励ましていきます。 |
| 計画的に勉強を進める習慣がつき、良い結果につながったと感じています。この調子を維持していきたいです。 |
| 本人も納得のいく結果が出たようで、次回に向けた目標も前向きに考えています。家庭でも応援してまいります。 |
| 積極的に質問するなど、主体的な学習姿勢が見られました。今後もこの姿勢を大切に育てていきたいです。 |
| 今回の成功体験が、他の教科にも良い影響を与えてくれそうです。全体の底上げを目指していきます。 |
| 達成感を得ることで、さらに意欲的に学習に取り組む姿が見られます。良い循環を続けていきたいです。 |
| 日頃の努力が評価される形となり、家族一同で嬉しく思っています。これを励みに引き続き支えてまいります。 |
テストの結果で平均点くらいだったときの親のコメント例文8選
テストの結果が平均点前後だったときは、「よく頑張ったね」という気持ちをまず伝えることが大切です。
親としてはもっと頑張ってほしいと思うこともありますが、努力や成長した点に目を向けて声をかけることで、子どもは前向きな気持ちになれます。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 全体的に平均的な点数でしたが、落ち着いて取り組む姿勢が見られ、前向きに頑張っていたようです。 |
| 基礎的な問題はしっかりと対応できており、学習内容の定着が進んでいると感じています。 |
| 学習習慣が身についてきたようで、以前よりも安定して取り組めるようになってきたと感じます。 |
| 学力に大きな波はなく、苦手分野の克服に少しずつ前向きに取り組んでいる様子が見られました。 |
| 平均点前後の結果に本人はやや悔しさを感じているようですが、次に向けて前向きに考えているようです。 |
| テストに向けて計画的に取り組む姿勢が見られ、学習への意識が高まっていると感じます。 |
| 授業中の理解は進んでいるようなので、今後は家庭学習との連携を意識して見守っていきたいです。 |
| 点数は平均的でしたが、本人なりに納得のいく取り組みができたようで、安心しています。 |
テストの結果で点数が低かったときのコメント例文8選
テストの点数が思わしくなかったとき、親としてはつい厳しい言葉をかけたくなるものですが、まずは子どもの努力や気持ちを受け止めることが大切です。
失敗は次へのチャンス!どこをどう改善していくか、家庭でも一緒に考えていく姿勢が、子どものやる気につながります。



落ち込む子どもを励ましつつ、次に活かす言葉を選んでくださいね。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 本人も結果を受け止めており、悔しさを次へのエネルギーに変えようとしています。 |
| 今回は振るわない結果でしたが、理解を深めるための取り組みを始めようとする様子が見られました。 |
| 問題の振り返りを丁寧に行っており、弱点の克服に向けて意識が高まってきています。 |
| 点数に関しては本人も反省しており、今後はより計画的に取り組めるよう声かけしていきます。 |
| 苦手意識のある教科に向き合う姿勢が芽生えており、少しずつですが意識に変化が見られます。 |
| 結果は思わしくありませんでしたが、諦めずに頑張る気持ちは強く、家庭でも応援していきます。 |
| 点数が低かったことで自己分析する姿が見られ、自発的な改善意欲を感じています。 |
| 今後の勉強方法を一緒に考えながら、家庭でも前向きに支えていきたいと思います。 |
マイペース・内向的な子のコメント例文8選
マイペースだったり内向的な子どもは、外から見えにくい努力をしていることが多いです。
「発言が少ない」「自分から質問しない」といった行動が気になるかもしれませんが、その子なりの成長や頑張りに目を向けてあげることが大切です。
先生にも家庭での様子や、内面の変化を伝えることで、より温かく見守っていただけるきっかけになります。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 本人なりに落ち着いた環境で学ぶことで、徐々に理解が深まってきているようです。 |
| 派手な成果はありませんが、日々コツコツと取り組む姿勢を大切にしてまいります。 |
| 自分のペースを守りながらも、継続して努力を重ねている様子を見守っています。 |
| 静かに努力するタイプですが、学習に対する関心が少しずつ高まっているようです。 |
| 結果よりもプロセスを重視し、丁寧に学ぼうとする姿勢を評価しています。 |
| 一人で集中して取り組む環境が合っているようで、家庭でもそのスタイルを尊重しています。 |
| 言葉数は少ないものの、自分なりの課題に向き合おうとする真面目さが伝わってきます。 |
| 目立たないながらも努力が積み重ねられていることを感じており、引き続き見守っていきます。 |
頑張っているが結果が出ない場合の親のコメント例文8選
一生懸命頑張っていても、すぐに結果に表れないことってありますよね。
そんなときこそ、子どもが「自分の努力を認めてもらえている」と感じられるコメントを残すことが大切です。
点数だけでは見えない成長や取り組みを先生に共有することで、学校でも温かく見守ってもらえるきっかけになります。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 学習に対する意欲は十分にあり、家庭でもよく頑張っている様子が見られました。 |
| 結果に表れていないものの、基礎学力は徐々に身についてきているように感じます。 |
| 取り組む時間や姿勢には成長が見られ、今後の成果に期待したいと思います。 |
| 本人も納得いかない結果だったようで、学習方法を見直そうとする意識が出てきました。 |
| 努力を続けていく中で、少しずつ理解度も深まっていると感じております。 |
| 一生懸命取り組んでいる姿を見ており、結果以上に過程を大切にしていきたいと考えています。 |
| 本人も悔しい思いをしており、前向きに次のテストに取り組もうとしています。 |
| 点数には直結しませんでしたが、前よりも学習に集中する時間が増えています。 |
成績が安定してきた子のコメント例文8選
成績に大きな波がなくなってきたときは、地道な努力が実を結びつつあるサインかもしれません。



継続することの大切さを認めてあげると、子どもにとっても大きな励みになります。
「家庭からのコメント欄」では、本人の頑張りや落ち着いて学習できている様子をさりげなく伝えていくと、先生にも安心して見守ってもらえるようになります。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 大きな波はなく、落ち着いて学習に取り組む習慣がついてきたようです。 |
| 安定した成績を維持している点を評価しており、今後も継続を意識してまいります。 |
| 授業内容への理解が着実に進んでいるようで、安心して見守ることができています。 |
| 苦手分野も以前よりは克服できてきており、成績のバランスが取れてきました。 |
| 焦らず一歩ずつ学んでいく姿勢が結果にもつながっているように感じます。 |
| 学習のリズムが整ってきたことで、安定した取り組みが可能になってきています。 |
| 一つひとつ丁寧に学習を進めており、結果にも安定感が出てきました。 |
| 今後は応用力の向上にも意識を向けつつ、着実な成長を支えていきたいと思います。 |
苦手な教科への意識が高まった子のコメント例文8選
苦手な教科に取り組もうとするのは、子どもにとってとても勇気のいることです。
点数や結果ではなく、「向き合おうとする姿勢」こそが本当の成長の証。
家庭からのコメント欄では、そんな変化を先生に伝えることで、学校との連携や子どもへのサポートがよりスムーズになります。



ここでは、苦手な教科への意識が高まってきた子どもに向けた前向きな親のコメント例文を8つご紹介します。
| 親のコメント例文 |
|---|
| これまで避けがちだった英語に対して、自主的に取り組む姿が見られるようになりました。 |
| 理科の用語を覚えるのが苦手でしたが、音読などの工夫をするようになってきています。 |
| 数学に対する抵抗感が和らぎ、自分から問題にチャレンジするようになってきました。 |
| 国語の読解が難しいと感じていたようですが、少しずつ粘り強く読めるようになってきました。 |
| 苦手教科でも“やってみよう”という気持ちが芽生えてきたことを嬉しく思っています。 |
| 間違いを振り返る姿勢が育ってきており、苦手分野に立ち向かう意識が見られます。 |
| 「苦手=やらない」ではなく、「苦手だから工夫しよう」と考えるようになってきました。 |
| できないことを受け入れ、少しずつ克服していこうとする姿勢を大切に支えていきたいと思います。 |
反省を次に活かそうとしている子のコメント例文8選
テストで思ったような結果が出なかったときに、反省して次に活かそうとする姿勢は、子どもの大きな成長の証です。
「どうして間違えたのか」「次はどうすればいいのか」と考えられるようになった時点で、学力以上の力が育っているといえます。
家庭からのコメント欄では、そうした前向きな変化を丁寧に伝えることで、先生との信頼関係も深まりやすくなります。



ここでは、反省を次に活かそうと努力するお子さんへのコメント例文を8つご紹介します。
| 親のコメント例文 |
|---|
| テスト後、自主的に振り返りを行っており、次回に向けた学習の改善を考えている様子です。 |
| 今回の反省点をノートに書き出し、自分なりに対策を立てようとする姿勢が見られました。 |
| 誤答の原因を一つずつ分析し、理解を深めようとしています。成長を感じます。 |
| 失点した部分を意識して復習し、次は間違えないようにと意欲的に取り組んでいます。 |
| 本人なりの改善案を話してくれるようになり、自主性が育ってきたと感じています。 |
| これまでにない視点でテストを振り返ることができており、大きな成長を感じます。 |
| 悔しさを前向きな力に変えて、次回はもっと良くしたいと話してくれました。 |
| 今回の失敗を無駄にせず、次回に繋げようとする姿勢を大切にしていきたいと思います。 |
目標設定や学習計画に意欲を見せ始めた子のコメント例文8選
「次はもっと点を取りたい」「この単元を復習しよう」など、学習に対して自分なりの目標や計画を立て始めたときは、大きな成長のタイミングです。
このような姿勢は、点数以上に評価されるべき立派な変化です。
家庭からのコメント欄では、その意欲や自主性が育ってきた様子を具体的に伝えることで、先生にも前向きな印象を持ってもらえます。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 自分で学習スケジュールを立てるようになり、目標に向かって努力しようとしています。 |
| 教科ごとに目標点を設定し、達成のために必要な学習内容を整理するようになりました。 |
| 週ごとの復習計画を立てるようになり、時間管理の意識が高まってきました。 |
| 計画通りに進まなかったときの振り返りもできるようになり、柔軟な姿勢が育っています。 |
| 具体的な目標を持つことで、日々の学習にも目的意識を持って取り組むようになりました。 |
| スケジュール帳を使って、自主的に学習記録を取るようになってきています。 |
| 計画を立てることが楽しいと話すようになり、主体的な姿勢が嬉しく感じられます。 |
| 目標達成の達成感を感じられるようになっており、モチベーションの維持につながっています。 |
高校受験を控えた中学3年生へのコメント例文8選
高校受験を控えた中学3年生の成績表には、「家庭からのコメント欄」での声かけもますます重要になります。
親としては焦る気持ちもありますが、子どもの努力や成長をきちんと認め、前向きな言葉でサポートしていくことが大切です。
ここでは、高校の受験に向けて頑張る子どもに寄り添った、自然で使いやすいコメント例文を8つご紹介します。



そのまま使ってもOKですし、お子さんの状況に合わせてアレンジしても◎です。
| 親のコメント例文 |
|---|
| 受験を意識するようになってから、自分から勉強時間を確保するようになり、意識の変化を感じています。 |
| 志望校に向けて具体的な目標を持ち始め、どの教科に重点を置くか考えるようになってきました。 |
| 模試の結果を踏まえ、弱点の洗い出しや勉強方法の見直しを自分なりに行うようになりました。 |
| 少しずつですが志望校の過去問題にも取り組み始め、受験に向けた実践力を養おうとしています。 |
| 部活動を引退してからは、集中して学習に取り組める時間が増え、学習リズムが整ってきました。 |
| 学校の各教科の先生のアドバイスを素直に受け入れ、自分の中で課題を整理するようになってきました。 |
| 受験に対する不安はあるものの、「今できることをやる」という前向きな姿勢が見られるようになりました。 |
| 志望校合格に向けて、プレッシャーに負けずコツコツと取り組む姿を家庭でも応援していきたいと思います。 |
NGな書き方とその理由
最後に、避けたほうがいいNGコメントもいくつか紹介しておきます。
- 「全く勉強せず困っています」(✕否定的すぎて先生も困惑)
- 「先生の教え方が合わないようです」(✕学校批判と受け取られる)
- 「○○点しか取れませんでしたが本人は満足しています」(✕ズレた認識に見える)
基本的に、感情をそのままぶつけるような書き方や、学校・先生を否定する内容は避けましょう。
コメント欄は“相談”ではなく、“協力の姿勢を見せる場”です。
読み手への配慮を忘れず、前向きな表現を意識してくださいね。
テスト結果が悪かった中学生への親のコメント例7選
テスト結果が悪かった中学生への親のコメント例7選を紹介します。



それでは、ひとつずつ解説していきますね。
否定せず気持ちに寄り添う
テストの点数が悪かったとき、つい「何やってたの?」なんて言いたくなってしまいますよね。
でも、まずは子ども自身が一番ショックを受けているということを思い出してあげてください。
ここで否定的な言葉をかけてしまうと、「親に認めてもらえない」と感じて心を閉ざしてしまうかもしれません。
「悔しかったね」「頑張ってたの知ってるよ」など、まずは気持ちに寄り添う言葉をかけてあげることで、子どもは心を開きやすくなります。
「わたしもミスして落ち込んだことあるよ」と、共感を示すのもおすすめです。
ここで大事なのは、“評価”ではなく“共感”です。
子どもが安心できる関係を築くための第一歩として、否定を避ける姿勢を意識してみてくださいね。
頑張った過程を認める
結果だけを見て怒ってしまうのはもったいないです。
たとえ点数が悪くても、「毎日コツコツ机に向かってたの見てたよ」といった声かけは、子どもにとって大きな励みになります。



中学生は、思春期の真っ只中で親の一言に敏感です。
「頑張ってたよね」と言われるだけで、「見てくれてたんだ」と自己肯定感が育まれます。
結果に表れない努力も、しっかり拾い上げてあげることが大切なんですよ。
評価されない努力って、ほんとにしんどいものですからね。
具体的な改善点を一緒に考える
次に大切なのは、「じゃあどうするか?」を一緒に考える姿勢です。
「ケアレスミスが多かったみたいだけど、どうしたら減らせると思う?」と問いかけてみてください。
子どもが自分で考えるきっかけにもなりますし、自主性を育むことにもつながります。
「解き終わったら5分見直しするようにしてみようか」といった具体策を提案するのもいいですね。
親がリーダーになって一緒に改善に向けて動いていく姿を見せると、子どもも前向きになれます。
一緒に乗り越える姿勢が、信頼関係を深めていきますよ。
次への目標を一緒に立てる
悪かった結果を責めるよりも、「次どうするか」を前向きに話すのが効果的です。
「次の数学で80点目指してみよう!」とか、「今回は悔しい思いしたから、次はちょっと作戦立てようか」とか。
未来に目を向けることで、子どもの気持ちも切り替えやすくなります。
「過去の結果」よりも「未来の目標」のほうが、エネルギーを注ぎやすいんです。



前向きな会話で、子どもの心に希望の光を灯してあげてくださいね。
励ましながらも事実は伝える
甘やかす必要はありませんが、頭ごなしに叱るのも逆効果です。
「今回は点数が低かったけど、次に生かせるチャンスだよ」など、やさしく事実を伝えてあげましょう。
大切なのは、言い方やタイミングです。
おやつの時間などリラックスしたタイミングで話すと、子どもも受け入れやすいです。
「事実+希望」がセットになった言葉は、子どもの心にスッと届きやすいです。
比較せずその子の成長に注目
「〇〇ちゃんは90点取ってたのに…」など、他人との比較は絶対NGです。
中学生は自分と他人を比べがちなので、親がそれを煽ってしまうと逆効果です。
「前よりも字が丁寧になってきたね」とか、「英語の文法しっかり覚えてたじゃん」など、成長したポイントに注目しましょう。
そうすることで、子どもも自分の伸びている部分を認識できて自信につながります。
点数だけがすべてじゃないことを、親が行動で示してあげましょう。
感情的にならず冷静に接する
最後に一番大事なこと、それは「感情的にならないこと」です。
親もショックだったり、ついガッカリしたりしますよね。
でも、そのままぶつけてしまうと、子どもは「失敗すると怒られる」と思い込んでしまいます。
それでは次のチャレンジが怖くなってしまいます。
まずは深呼吸して、落ち着いて話すように意識してみてください。
「どうしてこの点数になったか、一緒に見てみようか」といった声かけなら、子どもも素直に話してくれやすいです。
冷静な対応が、未来の行動を変えるきっかけになりますよ。
成績が良かったときにかけるべき親の声かけ5選
成績が良かったときにかけるべき親の声かけ5選をご紹介します。



それでは、それぞれの声かけを見ていきましょう!
素直に努力を褒める
まずはストレートに「よく頑張ったね!」と声をかけてあげましょう。
中学生になると、親の言葉を素直に受け取りづらくなりますが、「努力を認められる」のはやっぱり嬉しいものです。
ただし、「すごい!えらい!」だけで終わらず、「毎日ちょっとずつやってたの知ってるよ」と努力の過程に触れてあげるのがポイント。
それによって、子どもは「結果よりも努力が評価された」と感じ、自信になります。
褒めることで、次のチャレンジに向けてのモチベーションも上がりますよ!
どこが良かったか具体的に伝える
ただ「よかったね!」だけだと、子どもにとっては物足りないことも。
「数学の記述問題、ちゃんと考えて解けてたね」や「漢字テストの満点、すごく努力したんだね」といった具体的な褒め方が効果的です。
具体的なフィードバックは、「どこを頑張ればいいのか」「何が良かったのか」が明確になります。
それが次の勉強の指針にもなりますし、「ちゃんと見てくれてる」という安心感にもつながります。
ちょっと照れくさくても、ピンポイントで褒めてあげましょう。
次も頑張れるよう背中を押す
良い点数が取れたことに満足しすぎてしまうと、次に気持ちが向きにくいこともあります。
「今回良かったから、次はこの調子で頑張ろうね!」というように、さりげなく背中を押してあげましょう。
プレッシャーにならないように、「前よりすごく良くなってるね!」などの言葉で、自信とやる気を引き出してあげてください。
中学生はちょっとした言葉で大きく変わりますから、ポジティブな声かけがカギですよ。
テスト以外の部分も評価する
テストの結果ばかりにフォーカスせず、「提出物をしっかり出してたの偉いね」や「授業中に手を挙げてるの、先生が褒めてたよ」といった評価も大切です。
子どもは「自分の全部を見てもらえている」と感じると、親との信頼関係もより深まります。
また、テスト以外の努力も認めることで、「結果が出なかったときも見てもらえる」という安心感にもなります。
勉強以外の部分を褒める視点を持つことで、子どもにとって親は“味方”だと感じられるようになります。
親自身も喜びをシェアする
子どもがいい結果を出したときは、「すごくうれしい!お母さん(お父さん)も嬉しいよ!」と、親も一緒に喜びましょう。
中学生になってくると、「親に喜んでもらえること」がモチベーションにつながることも多いんです。
「一緒にケーキでも食べようか!」というような、ちょっとしたお祝いもおすすめですよ。
親が子どもの成果を一緒に喜ぶことで、家庭の中にポジティブな空気が流れます。
それがまた、次のチャレンジへの活力になるんです。
嬉しいときは、全力で一緒に喜ぶ!これ、大事です。
やってはいけないNGコメント5選


やってはいけないNGコメント5選をまとめました。



子どもを傷つけたりやる気をなくさせたりしないためにも、避けたい言葉をチェックしておきましょう。
「なんでこんな点数なの?」と責める
一番ありがちで、そして一番避けたいコメントです。
「なんでこんな点数なの?」という言葉は、責められているように聞こえてしまい、子どもは萎縮してしまいます。
特に中学生は、自分でも「やばい」と思っている場合が多いので、追い打ちをかけると心が折れてしまうことも。
代わりに、「何が難しかった?」と優しく聞くスタンスが◎です。
「原因を一緒に見つけよう」という姿勢で寄り添ってくださいね。
他の子と比較する
「〇〇ちゃんはもっといい点だったよ」なんて言葉、つい口にしてしまいがちですよね。
でも、これは子どもの自己肯定感を大きく削る原因になります。
誰かと比べられると、「自分はダメなんだ」と思い込んでしまうんです。
成長は人それぞれ、ペースも違うことを理解して、その子自身の変化や努力に注目してあげましょう。
比べるべきは「過去の自分」と伝えてあげるのも効果的ですよ。
感情的に怒る・無視する
感情が先に立ってしまい、怒鳴ったり無視したりしてしまうと、子どもは「見捨てられた」と感じてしまいます。
特に思春期の中学生は、親のちょっとした態度に敏感です。
「話しかけても無視された」「怒鳴られただけで終わった」となると、親との信頼関係も壊れかねません。
まずは深呼吸して落ち着く時間を取ってから、冷静に話すことが大切です。
感情よりも、建設的な対話を意識しましょう。
「やる気がない」と決めつける
結果だけを見て「やる気がないんじゃないの?」と言ってしまうのは危険です。
実際は頑張っていたけど、方法が間違っていたとか、体調が悪かったとか、さまざまな要因があるかもしれません。
「努力が足りない」と決めつけるよりも、「どうしたらうまくいくと思う?」と寄り添う姿勢が大切です。
一方的なレッテル貼りは、信頼を損ねる原因になります。
子ども自身が自分の中で原因を探せるように、導く声かけを意識しましょう。
親の期待を押しつける
「これぐらい取れると思ってたのに」や「もっとやれたでしょ」は、無意識のうちに親の理想を押しつけている言葉です。
期待があるのは悪いことではありませんが、それが“プレッシャー”になると逆効果です。
子どもが「親の期待に応えなきゃ」と感じすぎると、勉強がストレスになってしまいます。
「あなたがどれだけ頑張ったかを見てるよ」といった言葉のほうが、ずっと心に響きます。
親の期待は「信頼」に変えて伝えていくことが大切ですね。
中学生のやる気を引き出す親の関わり方5つのコツ



中学生のやる気を引き出す親の関わり方5つのコツをお伝えします。
中学生は反抗期も重なり、親の関わり方がとても難しい時期。
だからこそ、ちょっとした心がけが大きな違いを生みますよ。
家庭内の雰囲気を安心感で満たす
子どもが一番ホッとできるのは、やっぱり家庭です。
「失敗してもここに帰ってきたら安心できる」という空気を作っておくことで、学校や勉強にも前向きになれます。
親の機嫌が不安定だったり、ピリピリした空気が続いていると、子どもは不安になります。
笑顔で「おかえり」「今日はどうだった?」と迎えるだけでも、心はずっと軽くなりますよ。
家庭は“心の充電スポット”。その役割を意識するだけで、子どもの態度も変わってきます。
結果よりも過程を重視する
点数や順位ばかりに注目するのではなく、「どんなふうに頑張っていたか」を見てあげることが大切です。
たとえば、「毎日30分でも集中してたの、すごいと思うよ」や「漢字を何度も書いていたの、見てたよ」など。
こういった言葉は、「結果だけじゃないんだ」と子どもに安心感を与えます。
努力がちゃんと評価されると、「またやろう」という気持ちが芽生えるんですよね。
小さなことでも、プロセスに注目して声をかけていきましょう!
失敗も成長の一部と捉える
中学生はまだまだ成長の途中です。
ミスや失敗があるのは当たり前で、それをどう捉えるかがとても重要。
「次にどう活かせるか一緒に考えよう」と言ってあげるだけで、失敗が前向きな経験になります。
「失敗=怒られること」になってしまうと、新しいことに挑戦しなくなってしまいます。
でも、「失敗=学び」と感じられるようになると、子どもはどんどん成長していきますよ。
親のリアクションひとつで、子どもの視点は変わります。
会話の中で自然に学びを促す
「勉強しなさい!」と言うよりも、日常の会話の中でさりげなく学びにつなげる方法が効果的です。
たとえば、「このニュースってどう思う?」「今こんな言葉があるけど意味わかる?」など。
こうした会話の中で、自分の考えを言葉にする力が育まれます。
また、親の方から「知らなかった!教えてくれる?」と聞くスタンスもおすすめ。
子どもは“先生”になった気分で得意になれますし、自信もついていきますよ。
親も学び続ける姿勢を見せる
最後に一番のポイントは、親自身も学ぶ姿を見せること。
子どもは親の言葉よりも行動を見て育ちます。
本を読んでいたり、何かに挑戦している親の姿は、自然と「学ぶってかっこいい」と思わせてくれます。
たとえば、「お母さんも資格の勉強してるんだ」「お父さんも英語を学び直してるよ」と話してみてください。
家庭全体が“学ぶ空気”に包まれると、子どもも前向きになりやすくなります。
親も一緒に歩んでいる、という感覚が子どもにとっての安心材料になります。
まとめ


- 子どもの努力や姿勢に注目し、結果よりプロセスを肯定することが大切
テストの点数にかかわらず、日々の取り組みや変化を丁寧に言葉にすると、先生にも家庭でのサポートが伝わります。 - 改善点を書くときは“前向きな表現”を意識する
課題があっても、親がどう支えるかを示すことで、否定ではなく協力的な印象になります。 - コメントの締めくくりには、先生への感謝や今後の姿勢を添えると好印象
「今後ともよろしくお願いします」など、家庭と学校の連携を意識した言葉がポイント。 - 成績や性格に応じた具体的な例文を活用することで、無理なく書ける
高得点・平均点・低得点だけでなく、性格タイプや状況別の文例があると安心。 - NGコメントや避けたい言い回しも事前にチェックしておくことが重要
否定的な表現や他人との比較は避け、子どもの自己肯定感を傷つけない言葉を選びましょう。 - 「評価」ではなく「共感」と「寄り添い」が親のコメントの基本姿勢
中学生は繊細な時期。感情的にならず、冷静で温かな言葉をかけることが信頼関係を深めます。
成績表に書くたった一言、でもそこには親としての“まなざし”がにじみますよね。
良い結果でも思うようにいかなかった時でも、「見てるよ」「応援してるよ」という気持ちを、ほんの数行でどう伝えるか。
この記事では、そんな迷いに寄り添うヒントをたくさんご紹介しました。
点数の良し悪しに一喜一憂するのではなく、子どもの頑張りや成長の“かけら”を拾ってあげる。
その言葉は、きっと先生にも、そして何よりお子さんの心にも届くはずです。
「書かなきゃ」から「書いてあげたい」へ。



そんな気持ちになれるきっかけを、ぜひこの記事で見つけいただけたなら、嬉しいです!