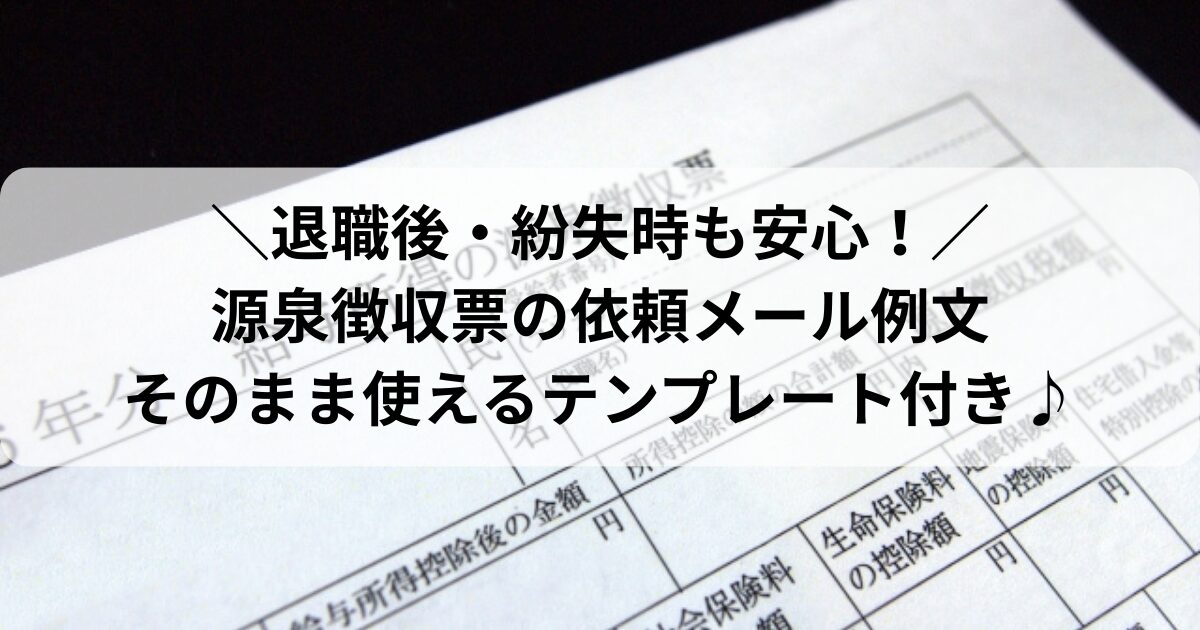源泉徴収票を依頼するとき、「どんなメールを書けば失礼にならないのかな?」と迷う方は多いです。
特に退職後や再発行の依頼では、相手にきちんと伝わる文章にしたいですよね。
この記事では、源泉徴収票メール依頼例文をケース別に紹介しながら、相手に伝わりやすく丁寧な依頼文を書くためのポイントをまとめています。
読んだその日から使える例文もあるので、状況に合わせて安心して活用できます。

丁寧で分かりやすい依頼メールを送って、スムーズにやり取りを進めていきましょう。
源泉徴収票を依頼する具体的なメール例文5選
源泉徴収票を依頼する具体的なメール例文5選について紹介します。



それでは、ケースごとに例文を見ていきましょう。
退職後に依頼する場合
退職後に源泉徴収票を依頼するケースは非常に多いです。
通常は会社から郵送されることが多いですが、時期や状況によっては依頼をしないと手元に届かないこともあります。
確定申告や転職先への提出に必要となるため、落ち着いた言葉遣いで依頼をしましょう。
以下に退職後に依頼するときの例文を示します。
| 件名 | 源泉徴収票送付のお願い(氏名) |
|---|---|
| 宛先 | 〇〇株式会社 人事部御中 |
| 本文 | 〇〇株式会社 人事部御中 お世話になっております。 〇月に退職いたしました〇〇(氏名)と申します。 昨年度分の源泉徴収票を送付いただきたくご連絡差し上げました。 お手数をおかけいたしますが、下記住所までご送付をお願いいたします。 ――――――――――――――― 〒000-0000 東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇〇〇(氏名) ――――――――――――――― お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 〇〇(氏名) 電話番号:000-0000-0000 メール:xxxx@example.com |
このように、退職した事実と氏名を明記し、送付先の住所をしっかり書くことがポイントです。
依頼する側が情報を整理して伝えることで、相手はスムーズに処理できます。
退職後に依頼する場合は「誰からの依頼か」が相手に分かりにくいため、必ずフルネームと連絡先を添えるようにしましょう。
これだけで信頼感がぐっと高まりますよ。
紛失して再発行をお願いする場合
源泉徴収票を紛失してしまった場合には、再発行をお願いする必要があります。
紛失は誰にでも起こり得ることですが、相手に余計な不安を与えないよう、落ち着いた依頼文にすることが大切です。
このとき重要なのは「紛失したため再発行をお願いしたい」という点を簡潔に伝えること。
そして、いつの年度分が必要なのかを正確に記載することです。以下に例文を紹介します。
| 件名 | 源泉徴収票再発行のお願い(氏名) |
|---|---|
| 宛先 | 〇〇株式会社 人事部御中 |
| 本文 | 〇〇株式会社 人事部御中 お世話になっております。 〇〇(氏名)です。 このたび、昨年度分(令和〇年分)の源泉徴収票を誤って紛失してしまいました。 確定申告に必要となるため、再発行をお願いできますでしょうか。 お手数をおかけして申し訳ございませんが、下記住所までご送付をお願いいたします。 ――――――――――――――― 〒000-0000 東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇〇〇(氏名) ――――――――――――――― ご多用のところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 〇〇(氏名) 電話番号:000-0000-0000 メール:xxxx@example.com |
再発行の依頼は「紛失しました」と正直に伝えれば問題ありません。
必要以上に詳しい理由を説明する必要はなく、むしろ簡潔にまとめた方が相手にとって分かりやすいです。
また、住所や連絡先を明確に書いておくことで、相手が確認のために余計なやり取りをする必要がなくなります。
依頼する側が情報を整えておくことは、相手への配慮にもつながります。
紛失は誰にでも起こり得ることなので、丁寧に依頼すれば快く対応してもらえることがほとんどです。
大切なのは落ち着いたトーンで、必要な情報をきちんと伝えることです。
在職中に人事部へ依頼する場合
在職中でも、住宅ローンの審査や各種申請のために源泉徴収票が必要になることがあります。
この場合は、所属している会社の人事部や総務部に依頼をするのが一般的です。
退職後の依頼とは違い、同じ会社に勤めている立場として失礼のないように、シンプルで分かりやすい文面を心がけましょう。
以下に在職中に人事部へ依頼する場合の例文を紹介します。
| 件名 | 源泉徴収票発行のお願い(氏名・所属部署) |
|---|---|
| 宛先 | 〇〇株式会社 人事部御中 |
| 本文 | 〇〇株式会社 人事部御中 お世話になっております。 〇〇部の〇〇(氏名)です。 〇〇の申請に必要なため、昨年度分(令和〇年分)の源泉徴収票を発行いただきたくご連絡いたしました。 可能であれば、社内便にてお送りいただけますと助かります。 ご多用のところ恐縮ですが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 〇〇(氏名) 内線:0000 メール:xxxx@example.com |
在職中の依頼では、所属部署や役職を明記しておくことがポイントです。
同じ会社の社員であることが一目で分かるので、相手が安心して対応できます。
また、受け取り方法については「社内便」「PDF添付」など希望を添えると、相手も対応をイメージしやすくなります。
希望がなければ「ご指定の方法で結構です」と書いておくのも良いでしょう。
在職中は相手とこれからも仕事で関わるため、依頼の際は特に礼儀正しくまとめることが大切です。
短い文でも丁寧にまとめることで、信頼関係を保ちながらスムーズに依頼ができます。
上司に依頼をお願いするとき
源泉徴収票が必要になったとき、まずは直属の上司に依頼をお願いするケースもあります。
人事部や総務部に直接送るよりも、上司に一言通してから依頼する方が自然な流れになる会社も多いです。
そのため、上司宛に依頼メールを送る際は、普段のやり取りよりも少し改まった表現を意識しましょう。
以下に上司へ依頼する場合の例文を紹介します。
| 件名 | 源泉徴収票発行依頼について(氏名) |
|---|---|
| 宛先 | 〇〇部 部長 〇〇様 |
| 本文 | 〇〇部 部長 〇〇様 お世話になっております。 〇〇(氏名)です。 このたび、〇〇の手続きのため、昨年度分(令和〇年分)の源泉徴収票が必要となりました。 恐れ入りますが、人事部に発行を依頼いただけますでしょうか。 必要な場合は、申請に関する書類や情報をご提示いたします。 ご多用のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 〇〇(氏名) 内線:0000 メール:xxxx@example.com |
上司宛の依頼では「お願いする立場」であることを意識し、柔らかく丁寧な表現を心がけることが大切です。
「お手数をおかけいたしますが」や「恐れ入りますが」といったクッション言葉を添えると、依頼のトーンが和らぎます。
また「必要があれば情報を提供します」と伝えると、上司も安心して人事部に依頼を回しやすくなります。
依頼をスムーズに進めるための一言として効果的です。
上司を通して依頼するケースでは、普段以上に礼儀正しさを意識すると良い印象を残せます。
シンプルながらも相手を立てる表現を使うことで、依頼がスムーズに進むでしょう。
代理で依頼する場合
源泉徴収票を本人ではなく代理で依頼する場面もあります。
例えば、体調不良や海外在住などの理由で本人が直接連絡できない場合です。
その際は「誰の代理で依頼しているのか」を明確にし、本人との関係性をしっかり伝えることが大切です。
以下に代理で依頼する場合の例文を紹介します。
| 件名 | 源泉徴収票送付依頼のお願い(代理:〇〇) |
|---|---|
| 宛先 | 〇〇株式会社 人事部御中 |
| 本文 | 〇〇株式会社 人事部御中 お世話になっております。 私は〇〇(氏名)の家族である〇〇(氏名)と申します。 このたび、本人が事情により直接ご連絡できないため、代理としてご連絡いたしました。 昨年度分(令和〇年分)の源泉徴収票を下記住所までご送付いただけますでしょうか。 ――――――――――――――― 〒000-0000 東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇〇〇(本人氏名) ――――――――――――――― ご不明な点がありましたら、下記の連絡先までご連絡いただけますと幸いです。 〇〇(代理人氏名) 電話番号:000-0000-0000 メール:xxxx@example.com お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 |
代理で依頼する場合、相手に「本当に本人の依頼なのか」という安心感を持ってもらうことが重要です。
そのため、本人との関係性をはっきり記載し、送付先の住所も本人名義で書くと信頼性が高まります。
また、代理人の連絡先を明記しておけば、相手が確認のためにスムーズに連絡できるので安心です。
相手に余計な負担をかけないように配慮すると、依頼が円滑に進みやすくなります。
代理での依頼は少し特別なケースですが、基本は「本人の依頼を代わりに伝える」という立場を明確にすることがポイントです。
丁寧に状況を説明することで、相手も安心して対応してくれるでしょう。
源泉徴収票をお願いするメールの書き方のポイント
源泉徴収票をお願いするメールの書き方について解説します。



それでは、順番に見ていきましょう。
依頼が必要になる場面
源泉徴収票を依頼しなければならない場面は、意外といろいろあります。
特に多いのは、退職後に新しい職場や確定申告のために必要になるケースです。
会社を辞めてしばらくすると、前の勤務先から自動的に送られてくることもありますが、状況によっては依頼をしないと手元に届かないこともあるんですよね。
ほかにも、うっかり源泉徴収票を紛失してしまったときや、転職先から提出を求められたときも依頼の必要があります。
この場合は再発行をお願いすることになるので、より丁寧な言葉遣いを心がけたいですね。
また、在職中でも、住宅ローンの審査や児童関連の申請などで「源泉徴収票が必要です」と言われることもあります。
そんなときは人事部や総務部に依頼をするのが一般的です。
特に、年度途中で必要になった場合は、担当部署にメールで依頼をするとスムーズに対応してもらいやすいですよ。
さらに、本人ではなく代理で依頼をする場面も考えられます。
たとえば、家族が事情で直接やり取りできない場合などですね。
その場合は、依頼者と本人の関係性を明記しておくと相手も安心して対応しやすくなります。
こうして見てみると、源泉徴収票を依頼する場面は退職後だけでなく、働いている途中や生活の中でも出てくることが多いです。
だからこそ、メールでの依頼の仕方を知っておくと安心なんですよね。
私自身も転職のときに「どうお願いすればいいんだろう」と悩んだ経験があります。
そんなときに、丁寧な依頼文の例文を知っておくと、焦らずに対応できるんですよ。
相手にも好印象を持ってもらえますし、手続きもスムーズに進みやすいですからね。
まずは「どんな場面で依頼が必要になるのか」を押さえておくことで、自分のケースに合わせて例文を使い分けやすくなります。
ここを理解しておくと、次に紹介する依頼メールのマナーも自然に身につけられますよ。
依頼メールを送るときの基本マナー
依頼メールを送るときの基本マナーを押さえておくことで、相手に不快感を与えず、スムーズにやり取りを進められます。
まず大切なのは「件名で要件を明確にする」ことです。
相手は日々たくさんのメールを受け取っていますから、件名だけで「源泉徴収票の依頼」であると分かるようにしましょう。
例えば、「源泉徴収票のご依頼について(〇〇)」といったシンプルで分かりやすい件名が適しています。
次に重要なのが「宛名と挨拶」です。
人事部や総務部に送る場合は「〇〇株式会社 人事部御中」、個人宛なら「〇〇様」といった具合に正しい敬称を付けてください。
そのうえで、冒頭には「お世話になっております。」といった挨拶文を必ず添えると、丁寧さが伝わります。
本文では「依頼の目的」「必要な理由」「希望する対応」を順番にまとめます。
例えば「確定申告のために、昨年の源泉徴収票を送付いただきたくお願い申し上げます。」といった表現です。
要点を整理して伝えることで、相手も対応しやすくなります。
また「期限」を添えておくことも大切です。
ただし「至急お願いします」など強すぎる言い方ではなく、「〇月〇日までにご対応いただけますと幸いです」と柔らかく伝えると印象が良いですよ。
そして最後に「感謝の一文」を忘れないこと。
例えば「お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。」と締めくくると、依頼メールとしてきれいにまとまります。
ちょっとした言葉遣いや表現の違いで、相手が受ける印象は大きく変わります。
形式的に思えても、こうした基本マナーを押さえておくと「気持ちのよい依頼メール」になりますよ。
私自身も以前、宛名をうっかり間違えてしまったことがあるのですが、そのときはとても恥ずかしかったです。
相手に手間をかけることにもつながるので、メールを送る前に必ず内容を読み直すことをおすすめします。
基本マナーを守るだけで、相手も「きちんとしているな」と感じ、対応もスムーズになります。
ちょっとした心がけですが、大きな違いを生むポイントなんです。
件名のつけ方で伝わりやすくする
件名はメール全体の第一印象になる部分です。
ここが分かりやすければ、相手もすぐに内容を把握して対応しやすくなります。
例えば「源泉徴収票の送付依頼(氏名)」といった形で、件名に要件と依頼者名を明記すると良いでしょう。
特に人事部や総務部のように複数の担当者がいる部署に送る場合は、誰からの依頼なのか一目で分かる工夫が役立ちます。
また「お願い」や「依頼」といった言葉を入れておくと、件名だけで依頼メールだと分かるので親切です。
「源泉徴収票について」だけでは漠然としてしまい、見落とされる可能性もあるため注意が必要です。
期限を強調したい場合には「源泉徴収票送付のお願い(〇月〇日まで)」と書くと、相手が優先順位を判断しやすくなります。
ただし「至急」「今すぐ」といった強い表現は避け、柔らかい伝え方を意識することが大切です。
件名をシンプルかつ具体的にすることで、相手に配慮のあるメールだと感じてもらえます。
メールが多い担当者にとっては、このちょっとした工夫がとても助けになるのです。
件名を工夫することは、依頼メールを丁寧に届けるための第一歩。
本文の内容がいくら丁寧でも、件名があいまいだと伝わりにくくなってしまうので、しっかり意識しておきたいポイントですね。
依頼内容を簡潔にまとめる
依頼メールでは、長すぎず短すぎない文章で要点を整理して伝えることが大切です。
相手が一読しただけで内容を理解できるように、必要な情報を簡潔にまとめましょう。
まず入れるべき要素は「依頼の目的」「対象となる年度や期間」「希望する対応方法」の3つです。
例えば「昨年分(令和〇年分)の源泉徴収票を送付いただきたくお願い申し上げます。
送付先は下記住所までお願いいたします。」といった形にすると、相手も迷わず対応できます。
文章をまとめるときは「一文一意」を心がけると分かりやすくなります。
ひとつの文に複数の要望を詰め込むと読みづらくなり、誤解を生む原因になるので注意が必要です。
また、希望の方法を明記することもポイントです。
「郵送での送付をお願いいたします」や「PDFでメール添付いただけますと幸いです」といった具体的な伝え方をすると、相手が対応しやすくなります。
依頼メールでは「なぜ必要なのか」を簡単に添えると、相手に安心感を与えます。
例えば「確定申告のため」や「転職先への提出が必要なため」といった一文を入れるだけで、依頼の背景が理解しやすくなります。
逆に、余分な情報や説明を長々と書くのは避けましょう。
丁寧であることと冗長であることは違います。短い言葉で的確に伝えることが、読みやすく感じてもらえるコツです。
依頼内容が整理されていると、相手は「分かりやすいメールだな」と感じ、迅速に動きやすくなります。
結局のところ、相手の手間を減らすことが、良い依頼メールにつながるのです。
依頼の文面を整えるときは、「必要な情報が網羅されているか」「余計な情報は入っていないか」を最終チェックしてから送信するようにしましょう。
ほんの数分の確認で、ぐっと伝わりやすいメールになります。
丁寧な締めくくりの書き方
依頼メールの最後は、相手に気持ちよく対応してもらえるように、丁寧な締めくくりを意識しましょう。
ここで一言添えるかどうかで、メール全体の印象が大きく変わります。
基本の形は「お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。」です。
これは依頼メールの定番表現であり、相手に対して感謝と配慮の気持ちをしっかり伝えることができます。
さらに一歩踏み込んで「ご多用のところ恐縮ですが、ご対応いただけますと幸いです。」のように書くと、より柔らかく丁寧な印象になります。
相手の状況を気遣う姿勢が伝わるので、温かみのある文面になります。
また、送付方法や期限を記載したあとは「お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。」と添えるとスムーズです。
要望を伝えた後に感謝の言葉を重ねることで、依頼の印象が和らぎます。
締めくくりの部分では、くどくならないようにシンプルさを保つことも大切です。
長い説明や繰り返しは避け、必要な一文で気持ちを伝えると、読みやすく心地よいメールになります。
最後に署名も忘れずに入れましょう。
フルネームや連絡先を記載しておくことで、相手が返信しやすくなります。
小さなことですが、信頼感を高めるための大切なポイントです。
丁寧な締めくくりは、相手に「気持ちよく対応したい」と思ってもらえるきっかけになります。
依頼メールは単なるお願いの文書ではなく、人と人とのやり取りです。
その意識を持つだけで、より良い関係につながっていきます。
源泉徴収票依頼メールで避けたい注意点4つ
源泉徴収票依頼メールで避けたい注意点4つを紹介します。



それでは、避けるべきポイントをひとつずつ確認していきましょう。
相手に負担をかける言い回し
依頼メールで最も注意したいのが「相手に負担をかける言い回し」です。
強い口調や一方的な依頼は、読む人に不快感を与える原因になります。
たとえ急いでいたとしても、「至急対応してください」「今すぐ送ってください」といった表現は避けましょう。
代わりに「〇月〇日までにご対応いただけますと幸いです」といった柔らかい表現を使うと、相手も気持ちよく対応できます。
期限を示しつつも、相手の状況に配慮した言葉遣いを意識することが大切です。
また「必ず」「絶対に」といった断定的な言葉も、受け取る側に圧力を与えてしまいます。
依頼はあくまでお願いであるため、「お願いできますでしょうか」「ご対応いただけますと助かります」といった表現が適しています。
さらに、長文で細かく要求を並べ立てるのも負担につながります。
必要な情報を簡潔にまとめることが、相手への思いやりになります。
メールは読みやすさも大切ですから、段落を分けて整理するとより親切です。
ちょっとした言葉の選び方で、相手に与える印象は大きく変わります。
負担を感じさせない言い回しを心がけるだけで、依頼がスムーズに進む可能性がぐっと高まります。
依頼メールは「お願いする立場」であることを忘れず、丁寧なトーンでまとめるようにしましょう。
結果的に、そのほうが早く正確に対応してもらえることにもつながります。
期限を曖昧にしてしまう
依頼メールでよくある失敗のひとつが「期限を曖昧にしてしまう」ことです。
源泉徴収票は書類の発行や送付が必要になるため、相手も準備に時間を要します。
期限をきちんと伝えていないと、相手の都合に任せる形になり、対応が遅れてしまうこともあります。
例えば「できるだけ早くお願いします」という表現は一見丁寧に見えますが、具体性がないため相手にとって分かりにくいのです。
相手が「来週で大丈夫だろう」と考えてしまう一方で、依頼者側は「今週中に欲しいのに」とギャップが生まれてしまうケースがあります。
そのため「〇月〇日までにご対応いただけますと幸いです」と期限を明確にすることが大切です。
もし多少の余裕を持たせたい場合は「〇月〇日までに可能であれば」と表現すると、柔らかさを残しつつ具体性を出せます。
また、どうしても期限が迫っているときには「〇月〇日までに必要なため、大変恐縮ですがご対応をお願いできますでしょうか」と伝えると良いでしょう。
強すぎず、かつ必要性を明確にできます。
期限を曖昧にしてしまうと、相手は後回しにしてしまう可能性があります。
逆に期限を伝えることで、相手もスケジュールを立てやすくなり、結果的に依頼がスムーズに進みやすくなるのです。
「急いでいる気持ちを抑えて、冷静に具体的な期限を伝える」ことを意識すれば、相手にも誠意が伝わり、安心して依頼に応じてもらえるでしょう。
個人情報の伝え方に注意する
源泉徴収票の依頼メールでは、氏名や住所などの個人情報を伝える必要があります。
しかし、このときに注意したいのが「情報の扱い方」です。
必要以上に詳しい個人情報をメールに書き込むと、万が一のリスクにつながることがあります。
依頼の際に最低限必要なのは「氏名」「住所」「連絡先」です。
これらを正しく明記すれば、相手は問題なく対応できます。
逆に、家族構成や不要な細かい情報まで書くのは避けましょう。情報が多すぎると相手も混乱してしまいます。
また、送付先の住所は必ず正確に記載してください。
郵便番号、都道府県、市区町村、番地まで省略せずに書くことで、相手が確認のために追加連絡をする手間を省けます。
丁寧に記載することは、自分にとっても相手にとっても安心につながります。
メール本文に記載する連絡先は「電話番号」「メールアドレス」程度で十分です。
必要に応じて会社名や所属部署を入れるとさらにスムーズです。
ただし、過剰に個人的な情報を盛り込む必要はありません。
個人情報を扱う場面では、見やすく整理することも大切です。
住所や連絡先を段落を分けて記載したり、罫線で囲んで見やすくするだけで、相手はひと目で確認できます。
依頼メールでは、必要な情報を「簡潔かつ正確に」伝えることを意識しましょう。
情報を適切にまとめることで、安心感を持ってやり取りを進めることができます。
誤字脱字や抜け漏れ
依頼メールで意外と多いのが、誤字脱字や必要事項の抜け漏れです。
ちょっとしたミスでも、相手にとっては「誰からの依頼か分からない」「どの年度分を送ればいいのか不明」といった混乱につながり、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に注意したいのは「氏名」「年度」「住所」の3つです。
氏名の漢字を間違えたり、年度をひとつずれて記載したりすると、再確認の手間が発生してしまいます。
また、住所の記載が抜けていると郵送ができず、再度やり取りをしなければならなくなります。
誤字脱字を防ぐためには、送信前に必ず文章を読み直すことが欠かせません。
声に出して確認したり、第三者にチェックしてもらったりすると、見落としが減ります。特に、数字や固有名詞は注意して確認すると安心です。
また、抜け漏れを防ぐには「依頼メールに必要な情報リスト」を意識しておくと便利です。



例えば以下のようなチェック項目です。
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 氏名(フルネーム) | ✔ |
| 必要な年度の明記 | ✔ |
| 送付先住所 | ✔ |
| 連絡先(電話・メール) | ✔ |
| 感謝の一文 | ✔ |
このようにチェックリストを意識して確認するだけで、誤字や抜け漏れをぐっと減らせます。
相手に余計な負担をかけず、依頼がスムーズに進むための工夫です。
依頼メールは一度送ってしまうと修正が難しいため、送信前の確認を習慣にしましょう。
小さな注意を積み重ねることで、誠実さや丁寧さが自然と伝わりますからね。
まとめ|源泉徴収票メール依頼例文で安心して依頼できる
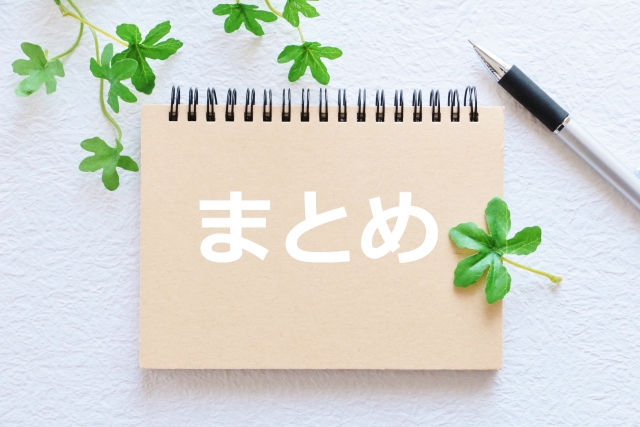
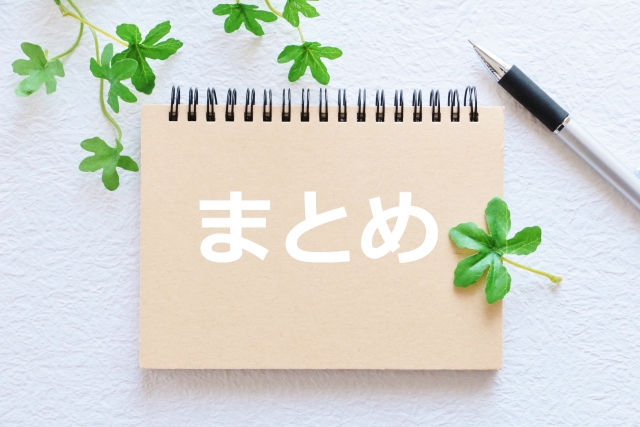
| 📌 ケース別の源泉徴収票依頼メール例文一覧 |
|---|
| 退職後に依頼する場合 |
| 紛失して再発行をお願いする場合 |
| 在職中に人事部へ依頼する場合 |
| 上司に依頼をお願いするとき |
| 代理で依頼する場合 |
源泉徴収票を依頼するメールは、状況に応じて文面を工夫することが大切です。
退職後や紛失、在職中など、ケース別の例文を参考にすれば、安心して依頼できるはずです。
件名で要件を明確にする、本文を簡潔にまとめる、連絡先を明示するなどの流れを意識すれば、相手に伝わりやすくスムーズなやり取りにつながります。
さらに、感謝の言葉や気遣いの一文を添えると、事務的なやり取りがぐっと温かいものになります。
誤字脱字や抜け漏れをチェックしてから送ることも忘れないようにしましょう。