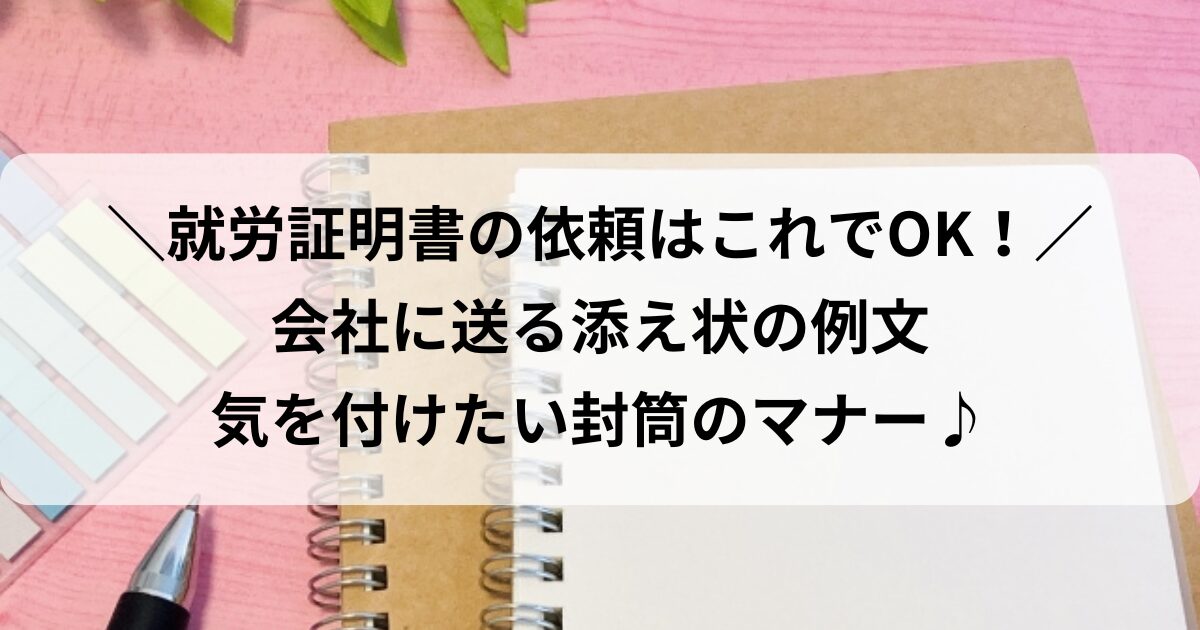会社に就労証明書の発行を依頼するとき、「どんな添え状をつければいいのか」「どのような書き方が適切なのか」と悩んでいませんか。
書類のやり取りは、適切なマナーを守ることでスムーズに進みます。
特に、忙しい人事部や上司に依頼する場合は、わかりやすく簡潔な添え状が鍵に。
この記事では、人事部へ直接送る場合や、上司を経由する場合の具体的な添え状の例文を紹介しながら、書き方のポイントを詳しく解説します。
さらに、手書きでもOKなのか、返信用封筒のマナーは?といった疑問にもお答えします。

就労証明書の依頼をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください!
会社に就労証明書の作成を依頼する際の添え状の例文と書き方を紹介
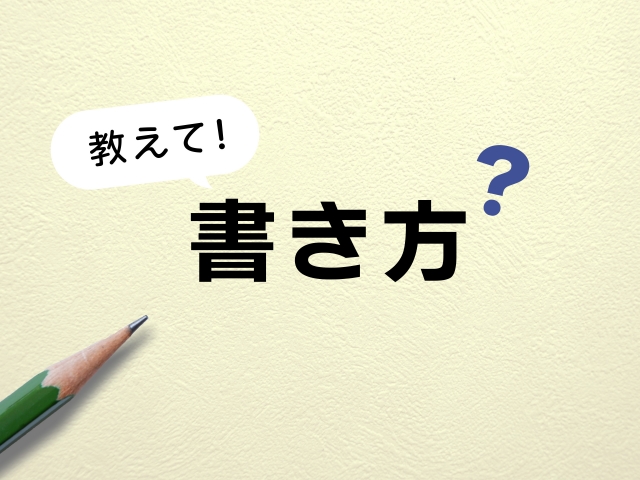
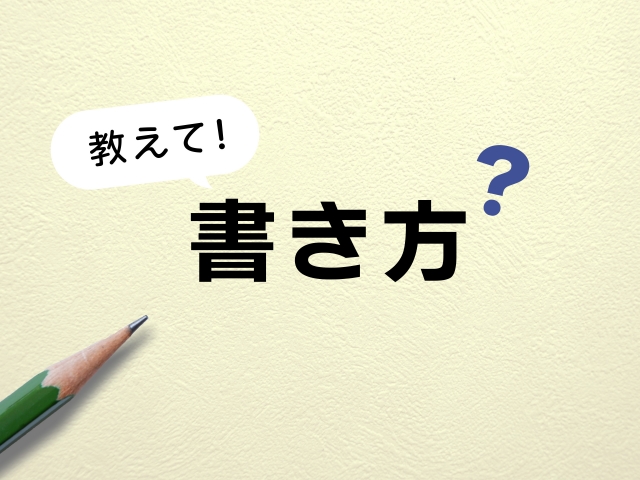
就労証明書を会社に依頼する際、添え状を同封することで、スムーズに発行してもらいやすくなります。
ただし、どのような文面にすればいいのか、どのような項目を記載すべきか悩む方も多いでしょう。
最初に、人事部に直接郵送する場合と、上司を通じて依頼する場合の添え状の例文を紹介し、その後、書き方のポイントを詳しく解説していきますね。
人事部宛に直接郵送する場合の添え状例文
人事へ直接郵送する場合の添え状例文(パターン1:シンプルなビジネス文書)
人事部 ご担当者様
お世話になっております。
〇〇部の〇〇(自分の名前)です。
下記の書類を同封いたしましたので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
<同封書類>
・就労証明書(1枚)
・就労証明書記入ガイド(1枚)
お手数をおかけしますが、〇月〇日までにご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。
<返送先>
〒○○○-○○○○
住所:〇〇〇〇〇〇〇〇
宛名:〇〇(自分の名前)
なお、ご不明点などございましたら、以下までご連絡いただけますと幸いです。
<連絡先>
電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
メールアドレス:〇〇〇@〇〇.com
お忙しいところ恐縮ですが、ご対応のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇部 〇〇課
〇〇(フルネーム・社員番号)
人事へ直接郵送する場合の添え状例文(パターン2:より丁寧な依頼文)
人事部 ご担当者様
いつもお世話になっております。
〇〇部の〇〇(自分の名前)です。
このたび、〇〇(例:子どもの保育園入園手続き)のため、就労証明書の発行をお願いしたく、ご連絡いたしました。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご対応いただけますでしょうか。
<同封書類>
・就労証明書(記入用紙)1枚
・記入の手引き 1枚
つきましては、恐れ入りますが、〇月〇日(期限)までにご記入のうえ、返信用封筒にてご返送いただけますと幸いです。
なお、記入方法や手続きに関してご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
<返送先および連絡先>
〒○○○-○○○○
住所:〇〇〇〇〇〇〇〇
宛名:〇〇(自分の名前)
電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
メールアドレス:〇〇〇@〇〇.com
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇部 〇〇課
〇〇(フルネーム・社員番号)



2つ目の添え状の例文はより丁寧な依頼文になっていますので、あなたの用途に応じて使い分けてくださいね!
上司を通じて就労証明書を交付してもらう場合の添え状例文
上司経由で郵送する場合の添え状例文(パターン1:シンプルかつビジネスライクな文面)
〇〇部長
お疲れさまです。〇〇(自分の名前)です。
このたび、子どもの保育園入園手続きに伴い、「就労証明書」の発行をお願いしたく、書類を送付いたしました。
お忙しいところ恐縮ですが、下記の書類をご確認のうえ、ご記入いただいた後、人事部へご提出いただけますでしょうか。
<同封書類>
・就労証明書(記入用紙)1枚
・記入の手引き 1枚
なお、提出期限は〇月〇日となっております。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
〇〇部 〇〇課
〇〇(フルネーム・社員番号)
上司経由で郵送する場合の添え状例文(パターン2:より丁寧で配慮を含めた文面)
〇〇部長
お世話になっております。〇〇(自分の名前)です。
このたび、子どもの保育園入園に際し、「就労証明書」の発行が必要となりました。
お手数をおかけし申し訳ございませんが、書類への記入および人事部へのご提出をお願いできますでしょうか。
<送付書類>
・就労証明書(記入用紙)1枚
・記入の手引き 1枚
期限が〇月〇日と迫っておりますため、お手すきの際にご対応いただけますと幸いです。
また、内容についてご不明な点がございましたら、直接人事部または私までご連絡ください。
業務ご多忙の折、恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
〇〇部 〇〇課
〇〇(フルネーム・社員番号)
こちらも2つ目の添え状の例文は、上司への配慮やお礼の言葉を加えた、丁寧な依頼文になっています。



ご自身の状況に応じて使い分けてくださいね。
また、就労証明書を発行してもらう際、上司を経由する必要がある場合は、事前にメールで依頼内容を伝えておくのがベストです。
これにより、スムーズに対応してもらいやすくなり、書類を送った際の確認もスピーディーになります。
パターン1:シンプル&端的な上司への依頼メール
端的かつビジネスライクに伝えたい場合に最適。
復職予定などには触れず、シンプルに就労証明書の依頼のみを伝えたい方向けの例文です。
件名:就労証明書発行のお願い(〇〇部 〇〇)
〇〇部長
お疲れ様です。〇〇(自分の名前)です。
このたび、子どもの保育園入園手続きのため、就労証明書の発行をお願いしたくご連絡いたしました。
就労証明書は会社の人事部に記入・発行を依頼する必要があるため、部長を経由して申請させていただきたく存じます。
後ほど、書類を郵送(または社内便)でお送りいたしますので、お手すきの際にご確認のうえ、必要な手続きを進めていただけますでしょうか。
書類の提出期限が〇月〇日となっておりますので、恐れ入りますが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。
<送付予定の書類>
・就労証明書(記入用紙)1枚
・記入の手引き 1枚
何かご不明な点がございましたら、お手数ですがご連絡いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
〇〇部 〇〇課
〇〇(自分のフルネーム)
パターン2:丁寧&配慮を含めた上司への依頼メール
こちらは、育休明けの報告や復職の相談も含め、上司とのコミュニケーションをとりながら依頼したい場合におすすめの例文です。
件名:就労証明書発行に関するお願い(〇〇より)
〇〇部長
ご無沙汰しております。〇〇(自分の名前)です。
長い育児休業をいただき、ありがとうございます。
現在、〇月の職場復帰に向けて準備を進めておりますが、その一環として、子どもの保育園入園手続きのために「就労証明書」の発行が必要になりました。
人事部に記入・発行をお願いする必要があるため、お手数をおかけいたしますが、部長を経由して申請を進めていただけますでしょうか。
後日、書類を郵送(または社内便)でお送りいたしますので、お手元に届きましたら、お手すきの際にご確認をお願いいたします。
なお、提出期限が〇月〇日と決まっておりますので、恐れ入りますが、お早めにご対応いただけますと幸いです。
また、復職時期について改めてご相談させていただきたいと思っております。
<送付予定の書類>
・就労証明書(記入用紙)1枚
・記入の手引き 1枚
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
〇〇部 〇〇課
〇〇(自分のフルネーム)
添え状の書き方のポイント
添え状は、単なる形式的な文書ではなく、依頼内容を明確にし、スムーズな対応を促すための重要な書類です。



以下のポイントを押さえて、適切な添え状を作成しましょう。
①宛名の書き方(送付先の明記)
宛名の書き方は、送る相手によって異なります。
✅ 人事部に直接送る場合 → 「〇〇会社 人事部 ご担当者様」
✅ 上司を経由する場合 → 「〇〇部長 〇〇様」
担当者の名前が分からない場合は、「ご担当者様」で問題ありません。
ただし、部署名は明確に記載し、適切に届くようにしましょう。
②書類の送付目的を明確に記載
何のために就労証明書を依頼するのかを簡潔に伝えます。
📌 例文
「子どもの保育園入園手続きに必要なため、就労証明書の発行をお願いいたします。」
就労証明書はさまざまな場面で利用されるため、目的を明記しておくと誤解がなくなります。
③同封書類の内容リストを記載する
送付した書類の名称と枚数を明記することで、書類の紛失や添付漏れを防ぐことができます。
📌 例
<同封書類>
- 就労証明書(記入用紙)1枚
- 記入の手引き 1枚
また、保育園や行政機関によっては、指定のフォーマットがあるため、その点も明記しておくとよいでしょう。
④期限を明記する
就労証明書の発行には時間がかかる場合があるため、「いつまでに必要か」をはっきり伝えることが重要です。
📌 例
「お手数ですが、〇月〇日までにご対応いただけますと幸いです。」



特に締め切りがある場合は、早めに依頼しましょうね!
⑤差出人の情報を記載する
何か不明点があった際に、会社からスムーズに連絡できるようにするため、以下の情報を記載します。
✅ 氏名(フルネーム)
✅ 所属部署・社員番号(社内での確認がスムーズになる)
✅ 電話番号・メールアドレス
✅ 返送先住所(郵送で受け取る場合)
⑥文面は簡潔かつ丁寧に
添え状は、長々と書く必要はなく、簡潔に伝えることが大切です。
「誰が、何を、いつまでに依頼したいのか」を明確に書きましょう。
このように、就労証明書の依頼には、適切な添え状を添えることで、よりスムーズに発行してもらうことができます。
送付先に応じた文面で、宛名・目的・期限・必要書類を明確に記載することがポイントです。



適切な添え状を準備し、スムーズに就労証明書を発行してもらいましょう!
就労証明書の添え状は手書きでも大丈夫?詳しく解説!


就労証明書を会社に依頼するときに、「添え状は手書きでもいいの?」 と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
特に、プリンターがない場合や、時間がないときに手書きで対応しても問題ないのか気になりますよね。
結論から言うと、添え状は手書きでも問題ありません!
ただし、ビジネスマナーとして意識すべきポイントがいくつかあります。
ここでは、手書きで書く場合の注意点やメリット・デメリット、適切な便箋の選び方などを詳しく解説します。
添え状は手書きでもOK!その理由とは?
会社に送る書類というと、パソコンで作成したほうがよいのでは? と思うかもしれません。
しかし、実際には手書きの添え状でも十分マナー違反にはなりませんし、多くの企業で問題なく受け取られています。
【手書きでもOKな理由】
- ビジネスマナーとして失礼にあたらない(手書きの文書が不適切とされるケースは少ない)
- プリンターがなくても対応できる(環境に左右されない)
- 手書きのほうが温かみがあり、丁寧な印象を与える
- 手書きの添え状を受け取ることに慣れている企業も多い
特に人事部や総務部門では手書きの添え状を受け取ることが一般的なケースもあります。
そのため、手書きだからといって失礼になることはほとんどありません。
手書きの添え状を書く際の3つの注意点
手書きで添え状を作成する場合、ただ書けばいいというわけではありません。



以下の3つのポイントを押さえることで、よりきれいで読みやすい添え状を作成することができます。
① 便箋を選ぶ(ルーズリーフやメモ用紙はNG!)
手書きの添え状を書くときは、便箋を使用するのが基本です。
📌 避けるべき用紙
❌ ルーズリーフや大学ノートの切れ端
❌ メモ帳や付箋(カジュアルすぎて失礼にあたる)
❌ 裏紙(ビジネス文書として不適切)
📌 適した用紙
✅ シンプルな白い便箋(罫線入り・無地どちらでもOK)
✅ ビジネス向けのレターセット(100均などでも購入可能)
✅ A4サイズの白い紙(きちんとした印象を与えたい場合)



100円ショップや文房具店で販売されている便箋を使うだけで、手書きでもきれいに見えますよ!
②読みやすい字を心がける(丁寧に書く)
手書きの添え状は、文字が読みにくいと逆に印象が悪くなってしまうことがあります。
そのため、できるだけ丁寧な字で書くことを意識しましょう。
【字を書くときのポイント】
- 黒のボールペンまたは万年筆を使用する(鉛筆や消せるペンはNG)
- 大きすぎず、小さすぎない適度なサイズで書く
- 1行の文字を詰め込みすぎない(適度な余白を意識)
- 修正テープや二重線は使わず、間違えたら最初から書き直す
字に自信がない場合は、下書きをしてから清書するのがおすすめです。
③ビジネスメールのような形式を意識する
手書きであっても、文章の構成は通常のビジネス文書と同じように整えて書く必要があります。
📌 基本の構成
- 宛名(人事部または上司の名前)
- 挨拶と送付の目的(就労証明書の発行を依頼する旨を記載)
- 同封書類のリスト(何の書類を送ったのか記載)
- 対応のお願い(期限などを伝える)
- 差出人情報(氏名・部署・連絡先など)
このように、手書きでもビジネス文書としての形式を意識すれば問題ありません。
〇〇部 人事ご担当者様
お世話になっております。
〇〇部の〇〇(自分の名前)です。子どもの保育園入園手続きのため、就労証明書の発行をお願いしたく、書類を送付いたしました。
<同封書類>
・就労証明書(1枚)
・記入の手引き(1枚)お手数をおかけしますが、〇月〇日までにご記入のうえ、ご返送 いただけますようお願いいたします。
<返送先>
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
〇〇(自分の名前)<連絡先>
電話番号:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
メールアドレス:〇〇〇@〇〇.comお忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇部 〇〇課
〇〇(自分の名前・社員番号)
手書きのメリット・デメリット
就労証明書の添え状は、手書きでも全く問題ありません。
「手書きでも大丈夫かな?」と悩んだら、便箋を使い、丁寧に書くことを意識すれば安心して送ることができますよ!
会社に就労証明書を依頼する際の返信用封筒について詳しく解説
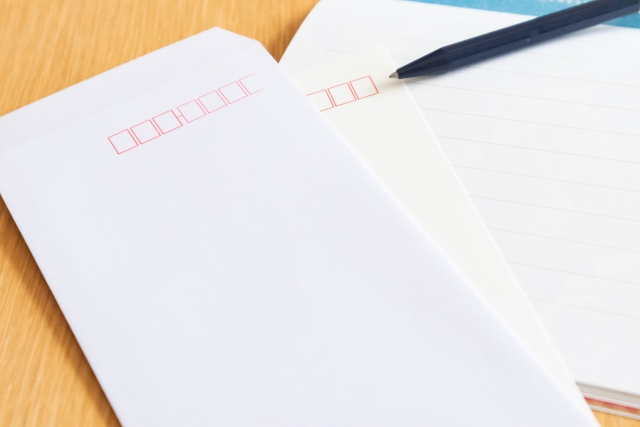
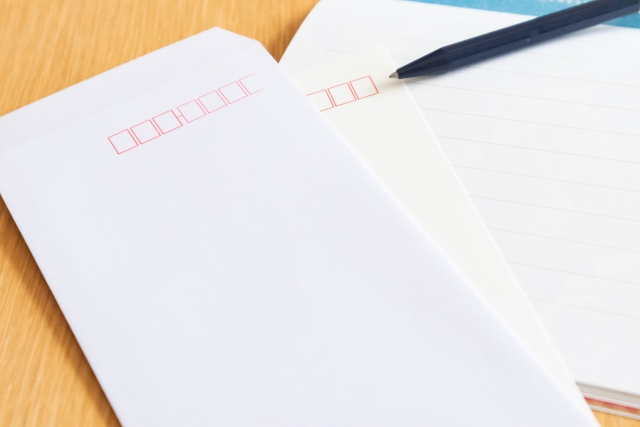



就労証明書を会社に依頼するとき、「返信用封筒を同封すべきか?」 迷う方も多いのではないでしょうか。
特に、会社の対応方針によっては不要な場合もあるため、適切な判断が必要です。
ここでは、返信用封筒を用意するべきケースや、書き方、切手の貼り方など詳しく解説します。
返信用封筒は必要?不要?会社の対応方針を確認しよう
返信用封筒を用意しなくてもよいケース
以下のような場合は、会社が送料を負担するため、返信用封筒を同封しなくても問題ありません。
✅ 人事部や総務部で書類の郵送対応をしてくれる会社
✅ 会社の規定で就労証明書の発行・送付が決められている場合
✅ 郵便代を会社の経費で処理することが一般的な業務フローになっている場合
特に、大企業では郵送費が会社負担になることが多いため、事前に確認しておくと無駄な準備を省くことができます。
返信用封筒を用意したほうがよいケース
以下のような場合は、返信用封筒を用意するとスムーズに対応してもらえます。
- 小規模な会社や個人事業主で、人事部がない場合
- 会社が郵便費を負担しない方針のとき
- 産休・育休中で会社とのやりとりに気を使いたい場合
- 過去に就労証明書を発行してもらったときに「返信用封筒を用意してください」と言われたことがある場合
特に、小規模企業や個人事業主の場合、会社側が郵送対応していないケースもあるため、返信用封筒を同封しておいたほうがスムーズです。
返信用封筒の選び方とサイズのポイント
返信用封筒を用意する場合、サイズや種類も重要です。
適切な封筒を選ばないと、会社側で扱いにくくなる可能性があります。
返信用封筒のおすすめサイズ



送られてくる就労証明書のサイズを考慮し、適切な封筒を選びましょう。
| 封筒の種類 | サイズ | 適した用途 |
|---|---|---|
| 長形3号 | 120×235mm | A4用紙を三つ折りにして入れる場合(コンパクトでコストを抑えられる) |
| 角形2号 | 240×332mm | A4用紙を折らずにそのまま送ってもらいたい場合(重要書類の場合におすすめ) |
用意する封筒のポイント
- 会社の書類が折りたたんでも問題ない場合 → 長形3号(一般的な長封筒)でOK
- 折りたたみたくない場合や会社のルールで決まっている場合 → 角形2号(A4サイズがそのまま入る封筒)を使用
- 郵便料金が変わるため、サイズごとの料金を事前に確認する
返信用封筒の宛名の書き方
返信用封筒には、自分の住所・氏名を記載しておく必要があります。
書き方のポイントを押さえておきましょう。
宛名の記載例
- 封筒の中央に「自分の住所・氏名」を書く
〒123-4567
東京都〇〇区〇〇町1-2-3
〇〇(自分の氏名) 行 - 「行」を「様」に訂正する余白を残す
会社が正式に郵送するときに「行」を二重線で消し、「様」に訂正するのがマナーです。 - 封筒の左下に「就労証明書在中」と書く(任意)
書類を紛失しないように、封筒の左下に「就労証明書在中」と記載しておくと、会社側でスムーズに処理できます。
切手の貼り方と郵便料金の目安
返信用封筒には、事前に切手を貼っておくのがマナーです。



ただし、封筒のサイズや重さによって料金が異なるため、適切な切手を選びましょう。
返信用封筒の郵便料金目安
| 封筒の種類 | 内容量 | 郵便料金 |
|---|---|---|
| 長形3号(A4三つ折り) | 50g以内 | 110円 |
| 角形2号(A4を折らずに送る) | 50g以内 | 140円 |
- 「簡易書留」や「速達」が必要な場合は、追加料金を調べておく
- 重さをオーバーしないように、郵便局で測ってもらうのがベスト
- 「料金不足」にならないよう、少し余裕をもった切手を貼る
返信用封筒を同封する際のポイント
返信用封筒を就労証明書の依頼書類と一緒に送る際には、次の点に注意しましょう。
✅ 返信用封筒は折らずにそのまま同封する(折りたたむと相手が使いにくくなる)
✅ 宛名・住所を事前に記入しておく(会社が手間を省けるように)
✅ 切手を貼っておく(料金不足で戻ってくるリスクを避ける)
このように、就労証明書を会社に依頼する際、返信用封筒が必要かどうかは会社によって異なります。
まずは、会社の方針を確認したうえで、必要であれば適切なサイズ・郵便料金で準備しましょう。
返信用封筒の準備が適切にできれば、会社側の負担も減り、よりスムーズに就労証明書を発行してもらえますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
就労証明書を詳しく解説
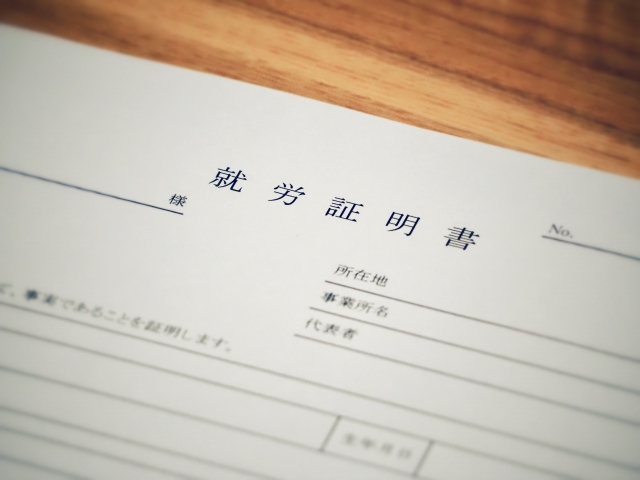
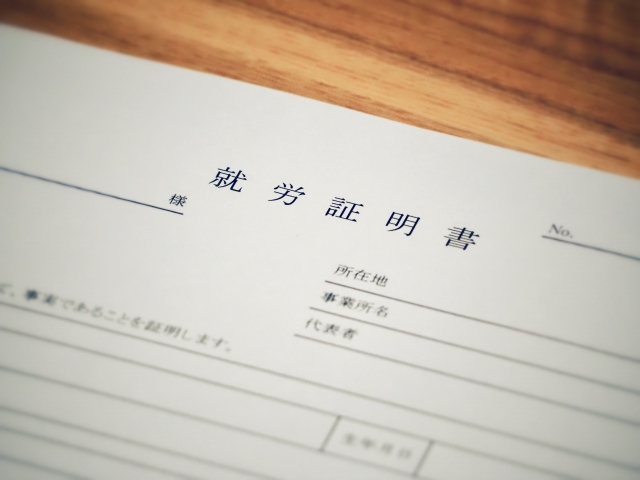
就労証明書は、働いていることを証明する公的な書類であり、保育園の入園手続きや住宅ローンの審査、各種行政手続きなどで必要になります。
ここでは、就労証明書の目的や書かれる内容、発行の流れ、注意点などを詳しく解説します。
就労証明書とは?その目的と役割
就労証明書(勤務証明書)は、特定の期間に雇用されていることを証明するための書類です。
発行するのは勤務先であり、公的機関や企業が「その人が本当に働いているのか」を確認するために利用されます。
どんな場面で必要になる?



就労証明書は、以下のような場面で求められることが多いです。
| 利用シーン | 目的 |
|---|---|
| 保育園の入園手続き | 親が就労していることを証明し、保育の必要性を示す |
| 住宅ローン・賃貸契約 | 安定した収入があることを証明し、ローン審査や契約の判断材料とする |
| 児童手当・扶養控除の申請 | 扶養義務者の就労状況を証明するため |
| 転職・退職時の手続き | 新しい勤務先やハローワークで、過去の雇用履歴を確認するため |
| ビザ申請・外国籍の手続き | 滞在資格や就労状況を証明するため |
このように、行政手続きや金融機関の審査など、さまざまな場面で求められる重要な書類です。
就労証明書にはどんな情報が記載される?
就労証明書には、勤務していることを証明するための基本情報が記載されます。
主な記載項目
✅ 雇用者(会社)の情報
- 会社名・住所・電話番号
- 事業主(代表者)名
✅ 労働者(本人)の情報
- 氏名・生年月日
- 雇用形態(正社員・契約社員・パート・アルバイトなど)
- 勤務開始日・雇用期間
- 勤務時間(フルタイム・時短勤務など)
- 勤務日数・勤務時間数
- 役職や業務内容
✅ 給与情報(必要な場合)
- 月収・年収
- 残業時間の有無
- ボーナスの有無
✅ 証明日・発行者の情報
- 証明書の発行日
- 会社の押印(社印または代表者印)
- 会社の担当者名・連絡先
就労証明書の発行手続き(依頼方法)
就労証明書は、勤務先の人事部や総務部などに依頼するのが一般的です。
ただし、小規模な会社や個人事業主のもとで働いている場合は、代表者に直接依頼することもあります。
発行までの流れ
①勤務先に依頼する
- 会社の人事部・総務部・労務課など、担当部署に「就労証明書の発行をお願いしたい」と連絡する。
- 企業によっては、申請書の提出が必要な場合もある。
②フォーマットを確認する
- 保育園や役所の手続きで必要な場合、自治体指定のフォーマットがあることが多いため、事前に確認しておく。
- 指定がなければ、会社独自のフォーマットを使用することもある。
③必要な情報を伝える
- 何の目的で使うのか、どの項目が必要かを事前に伝えるとスムーズ。
- 例えば「給与の記載が必要か」「就業時間の詳細が必要か」などを確認する。
④発行までの期間を確認する
- 会社によって、発行にかかる時間が異なるため、締め切りの1〜2週間前までには依頼しておくのがベスト。
⑤受け取りと内容の確認
- 発行されたら、記載内容を確認し、間違いがあれば早めに訂正を依頼する。
- 保育園や行政機関に提出する際は、原本を求められるケースが多いため、コピーでなく正式な書類を受け取るようにする。
就労証明書を依頼するときの注意点
就労証明書をスムーズに発行してもらうために、以下のポイントを押さえておきましょう。
①期限に余裕をもって依頼する
就労証明書の発行には、1週間〜10日ほどかかる場合があるため、ギリギリで依頼しないように注意。
特に、年度末や繁忙期は発行に時間がかかることがあるため、早めに手続きを進めるのがポイント。
②フォーマットを確認する
自治体や提出先ごとにフォーマットが異なることがあるため、会社が発行する前に必ず確認しましょう。
「会社指定のフォーマットでOKか」「提出先のフォーマットが必要か」を伝えておくと、手戻りが防げます。
③返信用封筒が必要か確認する
前述したように、会社によっては、就労証明書を郵送で送ってもらう場合、返信用封筒が必要になることもあります。



「会社負担か、返信用封筒が必要か」を事前に確認しておくとスムーズですね。
④受け取ったら内容を必ずチェックする
誤った情報が記載されると、手続きがスムーズに進まなくなるため、受け取ったら必ず確認しましょう。
特に、勤務開始日・勤務形態・勤務時間などの項目は、正確な情報が記載されているか確認することが重要です。
就労証明書は、保育園の入園手続きや住宅ローンの審査など、多くの場面で必要になる重要な書類です。
発行には時間がかかることがあるため、早めに会社に依頼し、フォーマットや必要事項を確認しておくことが大切ですね。
スムーズに手続きを進めるために、必要な書類を事前に準備し、余裕をもって対応しましょう!
まとめ
- 就労証明書を依頼するときは、添え状を同封するとスムーズに進む。 依頼の意図や必要な書類を明確に伝えることで、会社側の対応が早くなる。
- 人事部に直接依頼する場合と上司を経由する場合で、添え状の書き方が異なる。 それぞれに適した文面を選び、適切なマナーを守ることが大切。
- 添え状には「宛名・送付目的・同封書類・期限・連絡先」を明記する。 簡潔かつ丁寧な文章で、相手に伝わりやすいように心がける。
- 手書きの添え状もマナー違反ではないが、読みやすさに配慮が必要。 便箋を使用し、黒のボールペンで丁寧に書くとよい。
- 返信用封筒が必要かどうかは会社の対応による。 事前に確認し、必要な場合は適切なサイズ・郵便料金を準備することが重要。
- 就労証明書の発行には時間がかかることがあるため、早めの依頼がベスト。 フォーマットの有無を確認し、期限に余裕を持って申請するのがポイント。



本記事では、人事部へ直接郵送する場合と上司を経由する場合、それぞれのケースに適した添え状の例文を紹介しました。
就労証明書の依頼は、適切な文面と準備でスムーズに進めることができます。
相手に伝わりやすい添え状の書き方を学び、確実に発行してもらえるようにしましょう!