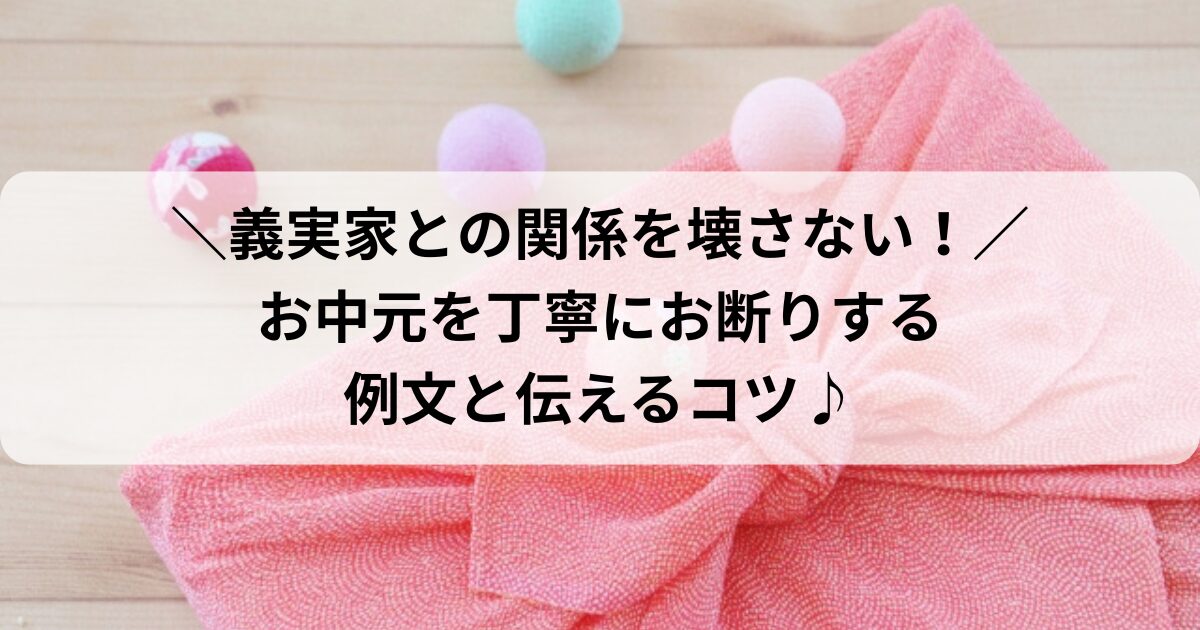「お中元、今年はもうやめたいな…でも義実家にどう切り出せばいい?」そんな悩みを抱えていませんか。

感謝の気持ちはあるけれど、毎年のやり取りが負担に感じることもありますよね。
断りたいけれど、義両親との関係は大切にしたい。
この記事では、失礼にならない断り方や、相手の心に響く伝え方、実際に使える例文まで、具体的にご紹介します。
無理なく、でも誠実に気持ちを伝えるためのヒントを、ぜひ手に入れてくださいね。
嫁の実家にお中元を断るときのマナーと例文
嫁の実家にお中元を断るときのマナーと例文について解説します。



それでは順番に見ていきましょう!
お中元を断るのは非常識じゃない
まず最初に言いたいのは、「お中元を断ること自体は、決して非常識ではない」ということです。
時代とともに、親戚付き合いや贈り物の文化も変わってきています。
最近では「形より気持ち」が重視される傾向が強く、お中元やお歳暮を廃止する家庭も増えてきました。
もちろん、急に何も言わずにやめるのは良くありませんが、ちゃんと「理由」と「気持ち」を添えて伝えれば問題なしです。
むしろ、無理して贈り続ける方が、関係にヒビが入るリスクもあるんですよね。
だから、「非常識かも…」と気にするよりも、「どう伝えるか」の方が大切なんです。
そのための方法や例文は、これからたっぷり紹介していきますので安心してくださいね。
相手に失礼なく伝えるポイント
大事なのは、「断る」という事実よりも、「伝え方」です。
たとえば、「生活が苦しいので」とストレートに言ってしまうと、相手に気を遣わせてしまうこともありますよね。
代わりに、「これからはお気持ちだけいただくことにしました」や、「贈り物のやりとりは、お互い負担にならない形にしたいと思いまして」など、前向きな理由に変換するのがおすすめです。
また、「感謝の気持ちは変わらない」というフレーズを添えると、相手も納得しやすくなりますよ。
ポイントは、“断る理由”と“感謝の気持ち”をセットで伝えること。これは鉄則です!
タイミングはいつがベスト?
お中元を断るタイミングって、実はめちゃくちゃ重要です。
おすすめなのは、お中元シーズンに入る少し前。つまり、6月下旬〜7月上旬あたりですね。
この時期なら、相手が「そろそろ用意しようかな」と考えているタイミングなので、無駄な準備をさせることなく伝えられます。
反対に、シーズンが終わったあとだと、「なんで先に言ってくれなかったの?」となる可能性もあるので注意が必要です。
「今年から控えさせていただきたいと思ってまして…」という自然な流れで伝えるとスムーズですよ。
嫁との相談・合意は必須
これはめちゃくちゃ大事です。絶対に、嫁さんと事前に話し合っておいてください。
嫁の実家に関わることを、夫側だけで決めてしまうと、あとで「なんで勝手に決めたの?」ってなりがち。
「こういうふうに思ってるんだけど、どうかな?」と一度相談して、2人の意見をすり合わせることが大切です。
そのうえで、嫁の口から伝えてもらうか、2人連名で連絡するのもアリですね。
義実家との関係に波風を立てないためにも、ここは慎重にいきましょう。
義両親との関係を壊さないために
最後に、いちばん大事なポイントです。
お中元を断ることで、義両親との関係が悪くなってしまっては本末転倒ですからね。
だからこそ、「断ること」が目的ではなく、「気持ちは変わらず感謝していますよ」という姿勢をちゃんと伝えることが大切です。
たとえば、お中元を断る代わりに「お盆に顔を出す」「年賀状で丁寧にご挨拶する」といった行動も効果的です。
モノよりも、心の通ったコミュニケーションが一番大事ってことですね。
断った後のフォローこそが、義実家との信頼関係を深めるチャンスになるかもしれませんよ。
LINE・メールで使えるお断り例文集


LINE・メールで使えるお断り例文集について解説します。



それでは、実際に使える文例を一緒に見ていきましょう!
LINEでの丁寧なお断り文
LINEでお中元のお断りをする場合、あまりに堅苦しいと逆に浮いてしまいます。
でも、カジュアルすぎると「え?そんな感じで断るの?」と誤解される可能性もあるので、丁寧語をベースにしつつ、やわらかく伝えるのがポイントです。
たとえば、こんな感じの文が使いやすいですよ!
お母さん、いつも温かいお心遣いありがとうございます。
恐縮なのですが、今後はお気持ちだけ頂戴することにさせていただければと思っております。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
この文章なら、堅苦しすぎず、でもきちんと感謝も伝わって、失礼な印象にはなりません。
また、「お気持ちだけで十分です」という言い回しは、やさしくて角が立ちませんよね。
メールで送る場合の例文
メールは文章量を多くできるので、より丁寧な表現が可能です。
たとえばこんな文章がベーシックで使いやすいです。
件名:お中元の件につきまして
お母さま
いつもご丁寧なお心遣いをいただき、誠にありがとうございます。
恐縮ではございますが、今後はお中元のお気持ちだけ頂戴できれば幸いです。
お互いに負担のない形で、これからも良いお付き合いができればと願っております。
今後とも変わらぬご厚情を賜れますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
文章のポイントは、「感謝→断り→今後のお付き合いへの配慮→お願い」の流れ。
この順番で書くと、相手も自然と受け入れやすくなります。
メールはあとあと見返されることもあるので、慎重に丁寧にが基本ですね。
カジュアルだけど失礼にならない表現
もし、義実家との関係がすごくフレンドリーで、あまりかしこまらない方がいい場合は、少し砕けた表現もアリです。
ただし、最低限の敬意と丁寧語は残しましょう。
例文はこちらです!
いつもいろいろとありがとうございます!
お中元、本当にありがたいのですが、気を遣わせてしまって申し訳なくて…。
これからはどうかお気持ちだけ頂けたらうれしいです。
こういった表現なら、温かい気持ちは伝えつつ、ストレートにお断りできます。
相手との距離感によって、こうした「フランクだけど丁寧」な言い方も選んでくださいね。
避けたいNGフレーズ
逆に、使ってしまうと角が立つかもしれないNGワードもあります。



以下のような言い方は避けた方が無難です!
- 「迷惑なのでやめてください」
- 「もう不要です」
- 「金銭的に厳しいので」
- 「そちらも大変でしょうから」
どれも、相手にネガティブな印象を与える表現です。
断る理由としても、「自分たちの事情」より「お互いの負担を減らすため」という前向きな理由に変換すると、相手も納得しやすいんです。
気持ちよく断るには、言葉選びがいちばん大事なんですよ。
電話・対面での伝え方と注意点
電話・対面での伝え方と注意点について解説します。



直接伝えるのは勇気がいりますが、その分、誠意も伝わりやすいですよ。
電話で断るときの流れと例文
電話でお中元を断る場合は、いきなり本題に入るより、まずは世間話や最近の様子を伺うところから入ると自然です。
そして、少し話した後で「実は…」という形で切り出すのがベスト。
以下が一例です。
こんにちは、いつもいろいろとありがとうございます。
実は、毎年いただいていたお中元の件でお話がありまして…。
本当にありがたく思っているのですが、今後はお気持ちだけ頂戴する形にさせていただければと思っております。
お互いに負担なくお付き合いを続けていけたらと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
電話だと相手の反応も分かりやすく、表情が見えないぶん声のトーンも意識すると丁寧に伝わりますよ。
ちょっと緊張するかもしれませんが、練習してからかけると落ち着いて話せます。
対面で伝えるときの言い方
対面で伝えるのは一番ハードルが高いですが、一番誠意が伝わる方法でもあります。
訪問時や食事のタイミングなど、落ち着いた雰囲気の中で話すのが理想です。



言い回しは基本的に電話と同じでOK。
違いは「表情」と「空気感」です。
あの…今日は、ちょっとご相談したいことがあって…。
毎年お中元を頂いて、本当に感謝しています。
ただ、今後はお気持ちだけ頂けたらと思いまして。
こちらからも何かをお贈りできているわけではないですし、どうしても心苦しくて…。
勝手を申し上げてすみませんが、よろしくお願いします。
大切なのは「申し訳ない気持ち」と「感謝の気持ち」を表情でしっかり伝えること。
その場で少し沈黙があっても、焦らずゆっくりと話してくださいね。
緊張しないコツと心構え
電話でも対面でも、「緊張してしまってうまく言えないかも…」って不安になりますよね。
そんなときは、紙に伝えたいことをメモしておくのがとても有効です。
話す順番や言い回しをあらかじめ考えておくだけで、心に余裕が生まれます。
あと、「緊張してるけど誠意を持って話そう」という気持ちが伝われば、相手はきっと理解してくれますよ。



完璧じゃなくても大丈夫です、伝えようとする姿勢が大事なんです。
話す前に準備すべきポイント
最後に、事前に準備しておくべきポイントをまとめておきます。
| 準備すること | 理由・ポイント |
|---|---|
| 断りの理由を明確にしておく | 説明に説得力が出る |
| 感謝の言葉を添える | 相手へのリスペクトが伝わる |
| 相手の気持ちを想像する | 冷静に対応できる |
| 話すタイミングを見計らう | 忙しい時間帯は避ける |
準備しておけばするほど、不安は減っていきます。
伝えるのは勇気がいりますが、きっとその誠意は相手にも伝わるはずですよ!
お中元を断ったあとのフォローが大切


お中元を断ったあとのフォローが大切です。



断ったからこそ、その後のフォローが相手との関係性を左右します。
代わりに感謝を伝える工夫
「お中元は遠慮したい」と伝えた後、そのままにしておくと、なんとなく空気が悪くなることもありますよね。
そんなときは、代わりに「感謝の気持ち」を別の形で伝えるのがとても効果的です。
たとえば、手書きのメッセージカードを送るとか、ちょっとした地元の名産を帰省時に渡すなど。
形式ばったお中元ではなく、「ちょっとした気遣い」の方が、実は喜ばれたりもします。
ポイントは、「形にとらわれず、心でつながる」ことなんですよね。
お年賀や手紙で気持ちを伝える
お中元を断ったあとに、「やっぱり気まずいかも…」と感じる方も多いです。
そんなときに使えるのが、年賀状や手紙という古くて強力なツール。
たとえば、年賀状にこんなひと言を添えてみてください!
あるいは、あえて手書きで一言メッセージを加えると、ぐっと温かみが増します。
メールやLINEでは出せない「手書きの良さ」って、やっぱり大事なんですよね。
今後のお付き合いに影響しないために
お中元のやりとりって、一見すると単なる「贈り物」ですが、実は人間関係を象徴する部分でもあります。
だからこそ、一方的に断るだけではなく、そのあとの「付き合い方」を意識することが超大事。
たとえば、何かのお祝い事があったときにはちゃんと贈り物をする、とか。
連絡をマメに取る、帰省のときには手土産を欠かさない、など。
「贈り物=付き合い」ではなく、「人と人とのつながり」を大切にすれば、きっと義実家とも良好な関係が築けますよ。
「もらう側」になったときの対応
中には、「もう送らないで」と伝えたのに、やっぱり義実家が送ってきた…というパターンもあります。
そんなとき、「言ったのに…」と思うより、「相手の好意」として素直に受け取るのが吉です。
そして、受け取ったら必ず「お礼の連絡」を忘れずに。
さらに、無理に返礼をせず、「お気持ちだけで嬉しいです」と改めて伝えるのがスマートな対応です。
大事なのは、相手の行動に「怒る」よりも「受け止める」姿勢。これが大人の対応ってやつです。
関係をこじらせないためにも、柔軟に対応していきましょうね!
トラブル回避!義実家との関係を良好に保つコツ
ここでは、義実家との関係を良好に保つコツをお伝えします。
義実家との関係って、ちょっとした行き違いで気まずくなることもありますよね。



でも、ちょっとした心がけでそれを防ぐこともできるんです。
断る前に嫁とすり合わせる
お中元を断ると決める前に、まずやっておきたいのが「夫婦での相談」です。
特に嫁の立場はデリケートなので、勝手に判断すると関係がこじれるリスクも…。
「こうした方がいいかなって思ってるんだけど、どうかな?」とやさしく意見を聞いてみましょう。
嫁の家族とのつながりを尊重する姿勢が、信頼にもつながります。
あくまで「二人で決めたこと」にしておけば、どちらにも角が立ちません。
義実家との温度差を理解する
価値観って、家庭によって本当にさまざまですよね。
「もうお中元なんて古いよね」と思っていても、義実家では「礼儀として当たり前」と思っていることも。
そういった“文化の違い”を前提に話を進めることで、衝突を防ぐことができます。
相手の立場に立ってみること。これだけで、対応のトーンも変わってきます。
理解しようとする姿勢が伝わると、相手もやわらかく受け入れてくれるんですよね。
フォローのひと言がカギ
どんなに丁寧に断っても、その後に「ひと言」添えるかどうかで印象がガラッと変わります。
たとえば、こんなフレーズがおすすめです:
本当にいつも感謝しています。
これからも変わらず、どうぞよろしくお願いします。
この一文だけで、グッと心の距離が縮まるんですよ。
断る=距離を置く、ではなく、より対等な関係になるためのきっかけとして使ってみてくださいね。
関係が悪化したときの対処法
万が一、相手が不快に感じてしまった場合も、焦らず冷静に対応しましょう。
まずは、素直に謝ることが第一ステップ。
「気を悪くさせてしまっていたら本当にすみません」と、誠意をもって伝えれば、相手の気持ちも少しずつほぐれていきます。
その後で、「やっぱりお中元だけじゃなく、普段のやり取りも大切にしたいと思っていて…」とフォローすれば、誤解もとけやすくなります。
何より、「関係を大切にしたい」という気持ちを言葉にすることが大事です。
どんな関係でも、軌道修正はできますからね!
まとめ


- お中元を断ること自体は失礼ではなく、伝え方が重要
- 感謝の気持ちを忘れず、前向きな理由を添えて伝えるのがコツ
- 断りを伝えるタイミングはお中元シーズン前がベスト
- 断る前に必ず配偶者と相談し、夫婦で方針を共有すること
- 断ったあとのフォロー(お盆の訪問や年賀状など)が関係維持のカギ
- 電話や対面の場合は、誠意ある態度と丁寧な言葉遣いを意識する
- 断った後も義実家との「心のつながり」を意識して関係を深める



嫁の実家にお中元を断るというのは、とてもデリケートなテーマですよね。
でも、失礼にならないように配慮しながら、感謝の気持ちを添えて丁寧に伝えれば、誤解を招くことはありません。
LINEやメール、電話、対面、それぞれの伝え方に合った例文を使うことで、相手の立場を尊重しつつ自分たちの意向もきちんと伝えられます。
そして何より大切なのは、断ったあとのフォロー。お礼や手紙、普段の気遣いが、義実家との関係を良好に保ってくれます。
一時の気まずさより、長い付き合いを見据えた行動を心がけていきましょう。