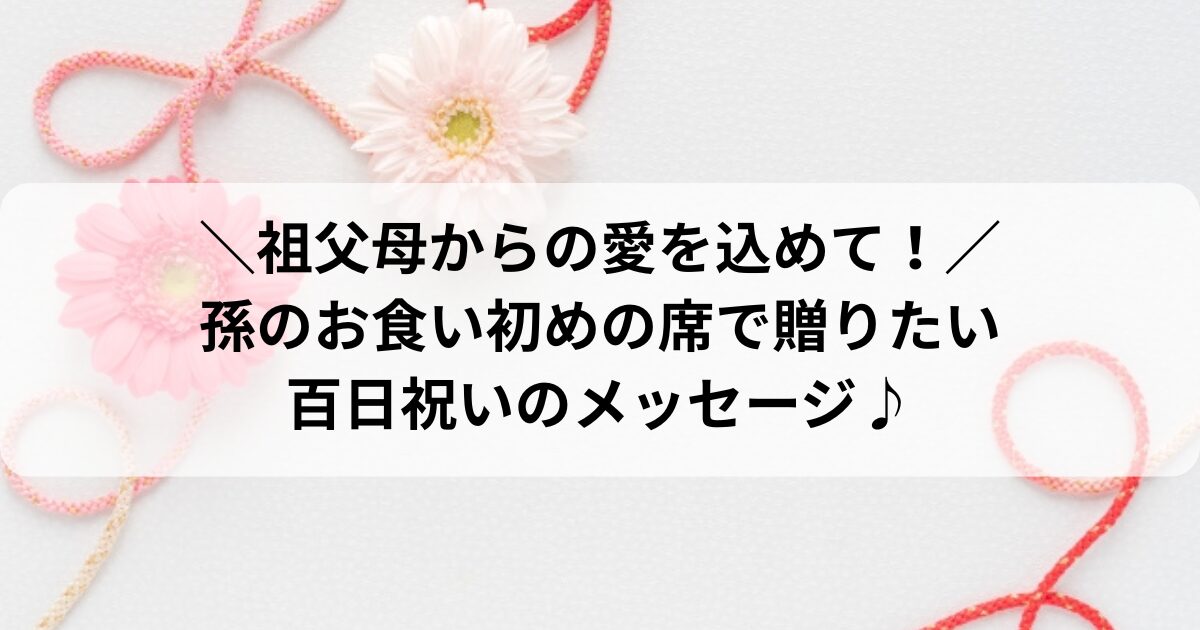お孫さんのお食い初め、おめでとうございます!
「何か特別なメッセージを贈りたいけど、どう書けばいいのか分からない…」そんな風に迷っていませんか。
祖父母だからこそ伝えられる、あたたかく心に残る言葉があります。
この記事では、お孫さんに贈りたいお食い初めの感動を呼ぶメッセージ例から、シーン別の伝え方、避けたい表現の注意点まで、丁寧にご紹介。

読み終えた頃には、「これなら伝えられそう!」と思えるヒントがきっと見つかりますよ!
祖父母から孫へ贈るお食い初めのお祝いメッセージの書き方と例文12選


お食い初めで祖父母が伝えたいお祝いメッセージとは
お食い初めで祖父母が伝えたいお祝いメッセージとは、孫の健やかな成長を願う気持ちや家族の絆を伝える温かい言葉です。



それでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきますね。
健やかな成長を願う気持ちを込める
お食い初めの一番の意味は「一生食べ物に困りませんように」という願いです。
祖父母にとっても、孫の健やかな成長を心から願う気持ちは自然と湧いてくるもの。
だからこそ、「元気に大きくなってね」や「健康でいてくれることが一番嬉しい」といったシンプルで優しい言葉が一番伝わります。
無理に飾った言葉を並べるよりも、普段の口調で温かく伝えると、子どもや親にもその愛情がちゃんと届きますよ。
筆者のおすすめは、「あなたの笑顔を見るたびに、元気をもらっています。どうかこれからも、健やかに成長してね。」といったように、“相手に語りかける”ように書くことです。
家族の絆を意識した言葉を添える
お食い初めは、赤ちゃんの節目だけじゃなくて、家族が一つになって成長を見守る行事でもあります。
だから、メッセージには「家族のつながり」や「一緒に育てていく」という温かい思いも込めると、より心に残ります。
たとえば、「みんながあなたの味方です」「おじいちゃんおばあちゃんも、ずっと応援しているよ」などの言葉は、家族の温もりを感じさせます。
こんな言葉は、将来お孫さんが大きくなったときに読み返して、きっと嬉しくなるはずです。
家庭によって言い回しは違ってOK。



無理にかしこまる必要はありませんよ!
お祝いの意味や伝統に敬意を表す
お食い初めは平安時代から続く、日本ならではの大切な行事です。
その歴史ある儀式に参加するということ自体、とてもありがたいことですよね。
だからこそ、「昔からの風習を大事にしてくれて嬉しいです」「お食い初めという節目を迎えられて感無量です」など、行事そのものへの感謝や喜びを言葉にするのも素敵です。
伝統に敬意を払いながら、今の気持ちも素直に綴ると、より深いメッセージになります。
若いご両親も、そういう言葉を聞くと「やってよかったな」と思えるきっかけになるかもしれません。
初孫ならではの感動も伝える
初孫のお食い初めなら、感動もひとしおですよね。
「初めて抱いたときの小ささが、昨日のことのように思い出されます」「あなたが生まれてきてくれたことが、何よりの宝物です」といった気持ちは、まさに“今しか伝えられない”言葉です。
もし涙がこぼれそうになるほどの想いがあるなら、それをそのまま文章にする勇気を持ってください。
そういう素直な気持ちほど、読み手の心に届くものです。
筆者も、祖父母からもらった手紙は今でも大切に残してますよ。
大人になって読み返すと、当時の情景が蘇ってじんわり心が温かくなります。
祖父母から孫へ贈るお食い初めのお祝いメッセージ例文12選
祖父母から孫へ贈りたい、お食い初めのお祝いメッセージ例文12選をご紹介します。
- フォーマルで丁寧な文章例
- カジュアルで親しみやすい文章例
- 初孫向けの特別な例文
- 二人目以降の孫への例文
- 父方祖父母からの文例
- 母方祖父母からの文例
- 手紙・カードで使いやすい例文
- LINEやメール向けの短文例
- プレゼントに添える一言例
- 感動的で涙を誘う例文
- ユーモラスで笑顔になる例文
- 祖父・祖母それぞれの口調で書いた例



おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちが伝わるように、シーン別に使いやすい文章をご用意しました。
フォーマルで丁寧な文章例
お食い初めの場にふさわしく、礼儀正しさを大切にしたい方に向けた文例です。
改まった場で読み上げたり、両家への配慮をしたいときに使いやすいスタイルになっています。
【メッセージ例】
ご誕生から百日を迎えられたとのこと、誠におめでとうございます。
こうして無事に「お食い初め」の日を迎えられましたこと、祖父母として心より嬉しく思います。
ご家族皆様の温かな愛情に包まれ、○○ちゃんがこれからも健やかに育たれますよう、心よりお祈り申し上げます。
この子の人生が喜びと愛に満ちたものでありますように。
皆様の末永いご多幸をお祈りいたします。
お祝いの席で読み上げても失礼にならず、かつ温もりを感じられる文面になっています。



目上の方がいる場でも安心して使えるので、特にフォーマルな式を予定している方にはおすすめですよ。
カジュアルで親しみやすい文章例
もっと身近な距離で、あたたかい気持ちを自然に伝えたい方におすすめなのが、カジュアルな文例です。
孫との距離が近いからこそ、リラックスした言葉選びが心に響きます。
【メッセージ例】
○○ちゃん、100日おめでとう!
ちょっと前まで、あんなに小さかったのに、もうお食い初めなんて、本当に早いね。
いつも動画や写真で元気そうな姿を見るたび、私たちまで元気をもらってるよ。
これからもいっぱい食べて、いっぱい笑って、元気に大きくなってね。
また抱っこできる日を楽しみにしてるよ~!
自然な口調の中にも、愛情と応援の気持ちがしっかり詰まっています。



「孫が成長していることが何より嬉しい」と感じている気持ちを、素直に表現してみてくださいね。
初孫向けの特別な例文
初めての孫へのメッセージは、特別な想いが込み上げてくるものです。
この文例では、その感動や出会いの記憶を丁寧に言葉にしています。
【メッセージ例】
○○へ
100日おめでとう。
あなたが生まれた日のことは、今でも鮮明に覚えています。
初めて抱っこしたとき、小さな体で一生懸命泣いていたあなたの姿に、じわっと涙が出ました。
おじいちゃんもおばあちゃんも、その瞬間から、あなたの味方であり続けたいと思ったよ。
あなたがこれから、どんな道を歩んでも、心から応援していくからね。
初めての孫として、たくさんの「はじめて」を見せてくれてありがとう。
初孫ならではの想い出がある方は、それをぜひ文面に込めてみてください。



心からの言葉は、どんな表現よりも強く温かく、未来の宝物になりますよ。
二人目以降の孫への例文
二人目、三人目の孫へのメッセージは、初孫のときとはまた違う愛情が溢れます。
上の子との関わりや、家族のにぎやかさも思い出しながら綴ると、自然と優しい文章になります。
【メッセージ例】
○○ちゃん、お食い初めおめでとう!
お兄ちゃん(お姉ちゃん)にそっくりな顔を見て、懐かしいなぁと思ったよ。
でも、泣き声も笑い顔も、ちゃんと“○○ちゃんらしさ”があって、家族の中に新しい風が吹いた気がしました。
にぎやかになる毎日、きっと笑顔がもっと増えるね。
兄弟(姉妹)仲良く、元気いっぱい育っていくのを、楽しみにしてるよ。



兄弟姉妹がいることへの安心感や期待を、さりげなく込めると伝わりやすいですね。
家族みんなで育っていく未来を想像して書いてみてください。
父方祖父母からの文例
父方の祖父母からのメッセージでは、「親として成長した我が子」への感慨を含めるとより深みが出ます。
【メッセージ例】
○○ちゃん、おめでとう。
君のお父さんが赤ちゃんだったころ、初めておむつを替えた日のこと、いまだに覚えているんだよ。
泣き声に右往左往していたあの頃から、まさかこんなに立派なお父さんになるなんて……。
そんな息子の子どもである君に会えて、本当に嬉しい。
この絆のリレーを、ありがたく、愛おしく感じています。
どうか、君がすくすくと、自分らしく育ってくれますように。
父方としての視点で、親子三世代のつながりを意識して書くと、深いメッセージになります。



「息子が親になった姿を見る喜び」も、ぜひ言葉にしてくださいね。
母方祖父母からの文例
母方の祖父母は、娘が親になる姿に感動しながら、孫との新しい絆を築いていきます。
親子二代にわたる思い出を絡めて書くと、読まれる側の心にも深く残ります。
【メッセージ例】
○○ちゃんへ
お食い初め、おめでとう。
あなたのママがまだ小さかった頃、一緒に作ったホットケーキや、おままごとの日々をよく覚えています。
あの子が今、あなたを抱いて同じように笑っている姿を見ると、胸がいっぱいになります。
これから、ママと一緒にたくさんのことを経験して、大きくなってね。
ずっとあなたの応援団でいるからね。
母方ならではの、娘への想いや記憶があたたかい雰囲気を生み出します。



孫とママの両方に「見守っているよ」と伝えるようにしてみましょう。
手紙・カードで使いやすい例文
コンパクトながら気持ちがしっかり伝わる文面は、カードや手紙にぴったりです。
シンプルな言葉でも、心がこもっていれば十分に伝わります。
【メッセージ例】
○○ちゃんへ
お食い初め、おめでとう。
あなたのまっすぐな目と、ぷにぷにのおててを見ているだけで、幸せな気持ちになります。
これから、毎日がワクワクとドキドキでいっぱいになりますように。
私たちは、いつもあなたの味方だよ。
カードに書くときは、文章の長さよりも“どれだけその子を思い浮かべて書いたか”が大事です。



読むたびに微笑んでしまうような、そんな言葉を選んでくださいね。
LINEやメール向けの短文例
今どきはSNSやLINEでメッセージを送る祖父母も増えています。
短い中でも気持ちがギュッと詰まった言葉が喜ばれますよ。
【メッセージ例】
○○ちゃん、100日おめでとう!
元気に泣いて、いっぱい飲んで、しっかり育ってるね♪
パパとママの愛情に包まれて、これからもすくすく育ってね。
また抱っこできる日を楽しみにしてるよ!
短くても、具体的な様子を想像しながら書くことで、心のこもったメッセージになります。



顔文字やスタンプを添えてもいいですね。
プレゼントに添える一言例
ギフトと一緒に贈るメッセージは、「品物+気持ち」が合わさることで、より思い出深いものになります。
短くても、記憶に残る言葉選びがポイントです。
【メッセージ例】
- この小さな贈り物に、あなたの未来への願いを込めました。
- あなたがこれからも、元気いっぱい、笑顔あふれる毎日を送れますように。
- この贈り物が、ずっとそばで見守ってくれますように。
プレゼントのテーマや用途とリンクさせて書くと、より意味のあるメッセージになりますよ。



品物の説明を軽く添えるのも親切ですね。
感動的で涙を誘う例文
特別な日だからこそ、心の奥にしまっていた想いを素直に綴りたくなる方も多いでしょう。
涙がこぼれるほどのメッセージは、一生の記憶に残ります。
【メッセージ例】
○○ちゃんへ
あなたが生まれてから、毎朝目覚めるのが楽しくなりました。
あなたの笑顔の写真を見るだけで、世界が優しく見えます。
100日という節目を迎えて、今まで無事に育ってくれたことに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。
これから先、辛い日があっても、あなたには私たちがついています。
どうか、思いきり笑って、泣いて、生きてください。
私たちは、あなたの全部を愛しています。
本音や涙を文章にするときは、無理に飾らず“そのままの言葉”で綴るのが一番です。



家族だからこそ書ける「深い愛」を表現してみてください。
ユーモラスで笑顔になる例文
お祝いごとに少し笑いを添えると、その場が和やかになります。
祖父母らしいお茶目さやユーモアがあると、読み手もほっこりしますよ。
【メッセージ例】
○○ちゃん、100日記念おめでとう!
歯もないのに、立派な鯛を前にしてドヤ顔してたらしいね(笑)
その調子で、どんなご飯でも元気にモグモグできる子になってね!
おじいちゃんは君におこられないように、最近甘いもの控えてるんだよ(笑)
また一緒におやつ食べようね♪
冗談の中にも愛情がにじむメッセージは、読んだ相手の心をゆるめてくれます。



その子の性格や家庭の雰囲気に合わせて、クスッと笑える一言を入れてみましょう。
祖父・祖母それぞれの口調で書いた例
「おじいちゃんらしい口調」「おばあちゃんらしい表現」にこだわると、よりリアルな想いが伝わります。



声が聞こえてくるような文面にしてみましょう。
【おじいちゃんより】
○○、100日おめでとう。
この前抱っこしたときの、あのぬくもり、今も手に残ってるぞ。
じいちゃん、若いころは山も登ってたんだ。
今度は○○と一緒にお散歩できる日を楽しみにしてるよ。
元気に育てよ。
【おばあちゃんより】
○○ちゃん、おめでとう♪
おばあちゃん、あなたに似合いそうなお洋服見つけてニヤニヤしちゃってます(笑)
ママに似て、ちょっと頑固なところもありそうだけど、それも可愛いよ。
たくさん食べて、たくさん笑って、大きくなってね。
あえてカジュアルな語り口にすることで、距離の近さや信頼が伝わります。
普段の会話と同じトーンで書くと、読み手も自然に笑顔になりますよ。
シーン別・形式別で考えるメッセージの贈り方


シーン別・形式別で考えるメッセージの贈り方をご紹介します。



それぞれのシーンに合った伝え方があるので、ぜひ参考にしてくださいね。
口頭で伝えるときのポイント
直接言葉で伝えるときって、実は一番緊張するんですよね。
でも、その分、気持ちがダイレクトに届くという魅力があります。
ポイントは、「短くてもいいから、ゆっくり目を見て伝えること」。
準備していた文章を全部覚える必要はありません。
「100日おめでとう。元気に育ってくれて嬉しいよ!」だけでも、十分心に響きます。
特に、お食い初めの食事中など、みんなが見ている前で話すのはハードルが高いですが、
赤ちゃんのほっぺに微笑みながら、そっと声をかけるだけでも立派なメッセージです。



ぜひ“ありのままの気持ち”を言葉にしてみてくださいね。
手紙・カードで贈る際の工夫
手紙やカードは、形に残るメッセージだからこそ、丁寧に気持ちを込めて書きたいですよね。
まずは、書き出しを「お食い初めおめでとう」などで明るく始めるのがポイント。
そのあとに、赤ちゃんの様子や、自分が感じている気持ちを素直に綴っていきます。
長さは気にせず、「自分が読み返したときに嬉しくなるか」を意識すると良いですよ。
手書きの場合は、多少の誤字や崩れた文字があっても、それが逆に“味”になります。
可愛い便箋や、家族写真を添えたカードにすると、一層喜ばれます。
また、少し先の未来を想像させる内容を盛り込むのもおすすめ。
「初めての一歩を踏み出す姿を見たいな」など、成長への期待が伝わりますよ。
形として残るからこそ、赤ちゃんが大きくなったときに読み返せる、最高の贈り物になりますね。
LINEやSNSでのマナー
最近は、遠方に住んでいたり、忙しかったりで、LINEやSNSでお祝いメッセージを送る祖父母も増えてきました。
デジタルなやり取りだからこそ、温かみのある言葉を選ぶことが大切です。
たとえば、「100日おめでとう!動画見てニコニコしてる○○ちゃんに癒されたよ」など。
写真や動画へのリアクションを添えると、会ってなくても“見守ってくれてる感”が伝わります。
句読点の多用や硬すぎる言葉は避けて、柔らかい表現を心がけましょう。
スタンプや絵文字を使いすぎると逆に軽く見えてしまうこともあるので、ほどほどに。
そして、「返信がなくても気にしない」ことも、SNSマナーの一つ。
相手の生活リズムを尊重して、温かく一方的な“応援メッセージ”に徹するのも素敵ですよ。
プレゼントに添える場合の注意点
プレゼントにメッセージを添えるときは、「贈り物とリンクした言葉」を入れると、より印象に残ります。
たとえば、お食事用のスタイを贈るなら「たくさん食べて、たくさんこぼして、すくすく育ってね」。
アルバムを贈るなら「今日のこの日から、たくさんの思い出が増えていきますように」など。
また、メッセージカードは“袋の中”ではなく、“目につく場所”にセットするのがコツ。
せっかくの想いが埋もれてしまわないように気をつけてくださいね。
形式は自由ですが、短すぎると味気なく、長すぎると読むのが大変なので、2〜3文くらいがベスト。
贈り物がただの“モノ”ではなく、“記憶に残るギフト”になりますよ。
お食い初めに避けるべきNGワードと注意点


お食い初めに避けるべきNGワードと注意点をご紹介します。



せっかくのお祝いですから、相手に安心して受け取ってもらえるような表現を心がけたいですね。
ネガティブな表現を避ける
「病気にならないように」とか「事故にあわないように」といった表現、よく見かけますよね。
でも、こうした“起こってほしくないこと”を連想させる言葉は、お祝いごとでは避けるのが基本です。
代わりに、「元気に育ってね」「笑顔が絶えない毎日を」など、ポジティブな表現に言い換えるのが安心。
とくに“まだ赤ちゃん”という大切な時期に、言葉の持つエネルギーは大きいです。
聞いたパパママが「ちょっと不安になる」ような言い回しは、無意識でも控えたほうがベターです。
伝えたいのは“守りたい”気持ちなので、それを前向きに変換してあげましょう。
言葉の選び方に世代差の配慮を
「昔はこれでよかったのに…」という言葉が、若いパパママには違和感に聞こえることも。
世代間の価値観のズレを埋めるためにも、なるべく今の子育て事情に寄り添った言葉選びが大切です。
例えば、「母乳のほうがいいよね?」とか「泣かせると肺が強くなる」といった昔ながらのアドバイス。
これ、昔は普通でも、今はプレッシャーになってしまうこともあるんです。
メッセージの中に入れる場合は、「私たちの時代はこうだったけど、今は違うみたいだね」と、やわらかく一言添えるだけで全然印象が変わります。
大切なのは「否定しないこと」と「違いを認めること」。
その姿勢が伝わると、メッセージはぐっと温かくなりますよ。
育児や出産に踏み込みすぎない
ありがちなNGが、育児や出産について“聞かれてもいないのに”触れてしまうことです。
お祝いの場で「寝返りはまだ?」「ミルクの量足りてる?」などと書いてしまうと、意図せず相手を追い詰めてしまうことも。
もちろん心配する気持ちは愛情なんですが、それは“聞かれたときだけ”伝えるのがスマート。
お祝いメッセージでは「頑張ってるね」や「愛情たっぷり育ててる姿が素敵」など、見守るスタンスがベストです。
“応援してるよ”の気持ちを主役にすることで、もらった人もホッとできますよ。
敬語や言い回しに注意する
気をつけたいのが「かしこまりすぎると、距離ができる」「くだけすぎると、失礼に聞こえる」というバランス。
たとえば「○○様、御機嫌麗しゅう…」なんて文語体で書かれても、現代の親世代は戸惑ってしまいます。
逆に、「マジでウケる」「めっちゃかわいい」など若者言葉すぎると、敬意が感じられなくなってしまうことも。
理想は、“自分の普段のしゃべり方+ちょっと丁寧め”くらいの文章。
「○○ちゃん、100日おめでとう。元気に育ってくれることが、なによりの幸せです」くらいがちょうどいいんです。
もし迷ったら、まわりの人に一度読んでみてもらうのも安心ですよ。
感動を呼ぶ!祖父母からのお祝いエピソード実例集
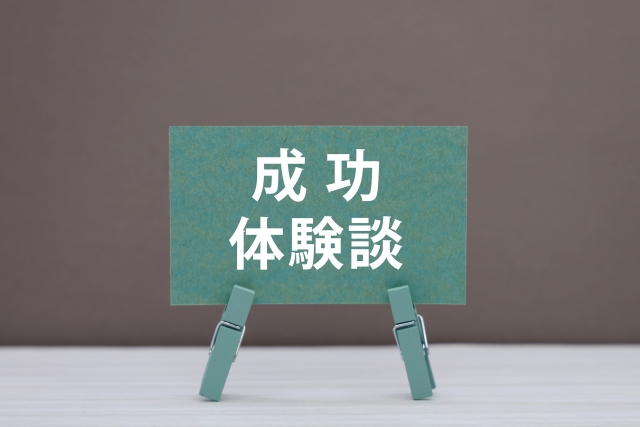
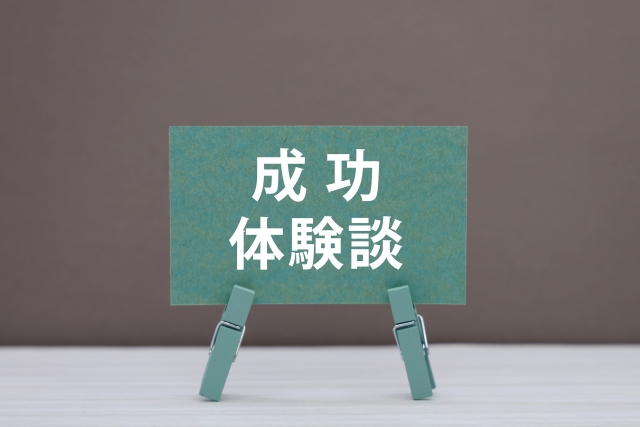
感動を呼ぶ!祖父母からのお祝いエピソード実例集をご紹介します。



“文章”だけじゃなく、“心”を贈った祖父母のエピソードは、受け取った家族の記憶に深く残ります。
手作りカードで喜ばれた話
あるおばあちゃんが、お食い初めの日に「手作りのメッセージカード」を贈ったエピソードがあります。
厚紙に色鉛筆で赤ちゃんの似顔絵を描いて、100日を祝うメッセージを添えたそうです。
そのカードには、ママが小さい頃に着ていた服の写真も貼られていて、「ママも同じように100日を迎えたよ」と綴られていました。
娘さん(ママ)はそれを見た瞬間に涙を流し、パパも「これは宝物になる」と写真を何枚も撮ったそうです。
手書きの温かさ、思い出の重なり、心からの言葉……どれもお金では買えない価値ですよね。
「手作り」というだけで、そこに“時間”と“想い”が込められていることが伝わります。
フォトアルバムにメッセージを添えて
こちらは、おじいちゃんが贈った“アルバム型のプレゼント”のお話。
生後から100日までの写真を印刷して、アルバムに1枚1枚コメントを添えたものです。
「このときの寝顔、初めて笑ってる気がしたなぁ」とか、「この日からおしゃぶりが大のお気に入り」など、思い出を丁寧に記録。
渡されたママパパは、「こんなに見守ってくれてたんだ…」と感激して、何度もページをめくったそうです。
実際に見た写真に、言葉が添えられていると、受け取る側も感情移入しやすいんですよね。
特別なカメラやセンスがなくても、「見たこと、感じたこと」をそのまま綴ることが最高の贈り物になります。
サプライズで感謝されたケース
ある祖母は、どうしても仕事の都合で当日参加できない代わりに、事前に“動画メッセージ”を用意していました。
孫の名前を呼びながら「元気に育ってくれてありがとう」と語るその姿に、家族みんなが涙。
ママは「声だけでも、すごくそばにいてくれてる気がした」と後日メッセージをくれたそうです。
実はこのおばあちゃん、スマホ操作が苦手だったので、おじいちゃんに撮ってもらって何度も撮り直しをしていたとか。
そのエピソードも含めて、家族のあたたかさが伝わるお祝いになったのだと思います。
「来られない=祝えない」ではないんですよね。
離れていても“伝えようとした気持ち”が、何よりの贈り物になります。
伝えた言葉に涙してくれた体験談
あるおじいちゃんが、席の乾杯のときにメッセージを読み上げたというエピソードがあります。
「君が生まれたと聞いた日、真っ先に名前を呼んだよ。まだ声も知らない君に向かって、嬉しすぎて叫んでしまった」
そんな言葉に、その場にいたママとパパ、親族も涙が止まらなかったそうです。
あとから聞いたら、「言葉にしたことで、自分自身も改めて感謝の気持ちに気づけた」と話していました。
メッセージって、“自分の気持ちを再確認する”時間にもなるんですよね。
ありのままの気持ちを口に出すことで、家族の絆がさらに深くなった、そんな素敵なお祝いの一日でした。
お食い初めのお祝いメッセージと一緒に贈りたいおすすめギフト10選


お食い初めのお祝いメッセージと一緒に贈りたいおすすめギフト10選をご紹介します。
- 名前入りの記念グッズ
- お食い初めの記念アルバム
- 実用的なベビー用品
- おしゃれなインテリア系ギフト
- 和風・伝統的なギフト
- 祖父母手作りのアイテム
- メッセージカード付きお菓子
- 写真フレーム付きメッセージ
- 名前ポエムのギフト
- 未来を応援するお守りや成長祈願グッズ



モノだけじゃなく、「意味がある」「記憶に残る」ギフトを選ぶのがポイントです。
名前入りの記念グッズ
赤ちゃんの名前が入ったアイテムは、世界にひとつだけの特別な贈り物になります。
お食い初めに合わせて、食器、スタイ、積み木などに名前を入れると、ぐっと記念感が増しますよ。
特に木製のアイテムは、長く使えるうえにナチュラルで温かみもあります。
後から見返しても「これ、お祝いのときにもらったよね」と思い出がよみがえります。
ひと手間かけた分、気持ちもちゃんと伝わります。
お食い初めの記念アルバム
お食い初めの写真を収める専用のアルバムも人気です。
表紙に赤ちゃんの名前や日付を入れられるものも多く、イベントごとにページを埋めていけるタイプもあります。
そこに祖父母からのメッセージを一言添えておくと、見返すたびにじんわり嬉しくなりますよ。
アルバムは、親が忙しい中でも“記録を残すきっかけ”になります。
写真好きなパパママには特に喜ばれる贈り物です。
実用的なベビー用品
「すぐ使えるものが嬉しい」というパパママの声も多いです。
おむつケーキ、離乳食用のスプーンセット、洗えるブランケットなどは実用性バツグン。
ポイントは、すでに持っていそうなものと被らないようにすること。
事前にさりげなく確認しておくか、複数持っていても困らないアイテムを選びましょう。
「使ってもらえる=想いが生活に溶け込む」ことなので、十分気持ちは伝わりますよ。
おしゃれなインテリア系ギフト
ちょっと特別感を出したいなら、部屋を彩るインテリア系のギフトもおすすめ。
例えば、木製の命名ボード、星型ライト、ファブリックポスターなど。
写真映えするデザインで、お食い初め当日の装飾にもぴったりです。
メッセージと一緒に贈れば、“写真に残る思い出”としても印象に残ります。
和風・伝統的なギフト
お食い初めという日本の伝統行事に合わせて、和風のギフトを選ぶのも粋です。
漆器の器セットや、桐箱に入った祝箸などは、特別感があります。
「日本の文化を大切にしてほしい」という想いを込めるのにもぴったり。
あえて“今っぽくないもの”を贈ることで、行事の意味をより引き立てられます。
祖父母手作りのアイテム
手編みの帽子や、名前入りの刺しゅうスタイ、写真入りの手作りアルバムなど、ハンドメイドの贈り物はやっぱり格別。
「時間をかけて準備した」こと自体が大きな愛情表現になります。
不器用でもOK。完成度より、“気持ちのこもり方”が大事です。
家族にしか作れない“世界に一つ”の贈り物として、長く愛されるアイテムになりますよ。
メッセージカード付きお菓子
お祝い用のお菓子に、祖父母のメッセージカードを添えるだけでも素敵なギフトになります。
最近は「名入れマカロン」や「オーダーお祝いクッキー」など、見た目にも華やかなお菓子も多いです。
赤ちゃんが食べられなくても、パパママへのご褒美に。
箱を開けた瞬間に笑顔がこぼれる、そんな演出を狙ってみてくださいね。
写真フレーム付きメッセージ
写真立てに、赤ちゃんの名前や日付を刻印したり、メッセージが印刷された台紙を入れたり。
インテリアとしても飾れるし、成長記録としても楽しめる優れものです。
祖父母が撮ったお気に入りの一枚を選んで、メッセージを添えて贈るのも素敵です。
「このときの笑顔、宝物だよ」なんて書いてあったら、きっと喜ばれますよ。
名前ポエムのギフト
名前の文字を織り込んで作る“名前ポエム”は、特別感が強く、感動されるギフトのひとつ。
「名前に込められた意味」や「家族の願い」を形にするので、飾るだけで存在感抜群です。
オーダーメイドできる作家さんも多く、最近はカジュアルでおしゃれなデザインも増えています。
「世界にひとつ」を求めるなら、間違いなくおすすめです。
未来を応援するお守りや成長祈願グッズ
「これからの人生を、安心して元気に過ごせますように」という願いを込めた、成長祈願のお守りやグッズも人気です。
神社でいただける“子ども守”や、“成長祈願”の名入りお守り、誕生日にちなんだ干支の飾りなど、さりげなく想いを伝えられるものが多くあります。
パパママへのサポートとして、「家族みんなでこの子を見守っていきたいね」というメッセージを添えるのも素敵ですね。
中には、誕生石や干支をモチーフにした雑貨に願いごとを込められる商品もあります。
かしこまらずに、でもちゃんと気持ちが届く、そんな“見守りアイテム”として贈るのにぴったりですよ。
孫の成長を祈る“想いのこもった言葉”の選び方
孫の成長を祈る“想いのこもった言葉”の選び方について解説します。



どんな言葉を選べば、「この子の人生にそっと寄り添えるか」…そんな気持ちで考えてみましょう。
短くても心に残る言葉選び
実は、心に残る言葉って「長い文章」よりも「短いけど強い言葉」だったりします。
たとえば、「そのままで、いいんだよ」とか、「あなたは愛されてるよ」。
言葉自体はシンプルでも、その背景に“どれだけの思いがあるか”が伝わると、ぐっと心に響くんです。
特に赤ちゃんの成長を願うメッセージには、「元気でいてね」「笑顔が何よりの宝物」など、短く温かい表現が向いています。
長く書くことが苦手な方でも、こうした“ひとこと”があるだけで、印象はまったく違います。
それはまるで、ポケットの中にいつも入れておける“心のお守り”のような存在になりますよ。
「これから」に向けた励まし
お食い初めは、これから先の人生を想う始まりの行事。
だからこそ、“これからの未来”に目を向けた励ましの言葉を選ぶのもおすすめです。
「いっぱい挑戦してね」「転んでも立ち上がれる子になってね」
そんな言葉には、祖父母としての人生経験がにじみ出て、重みと温かさを感じさせてくれます。
決して“上から目線”にならないよう、あくまでも“応援”の気持ちで。
「どんな君でも大丈夫だよ」と、未来に向けたエールを贈りましょう。
家族みんなの気持ちを込める
メッセージは、祖父母一人からのものでも、“家族みんなの想い”として書くとより一層あたたかくなります。
「パパもママも、あなたのことが大好きだよ」「家族みんなが、あなたのことを見守っているよ」
そんな風に、周りの人たちの気持ちも一緒に乗せることで、赤ちゃん自身が“支えられている”ことを感じやすくなります。
さらに兄弟やいとこ、おじさんおばさんの名前もさりげなく入れると、“家族のつながり”がよりリアルになります。
メッセージが、家族の「心の寄せ書き」のようになると、きっと何年経っても宝物になりますね。
一生の記念に残る文章の工夫
将来、孫が大きくなったとき、「あのとき、こんな言葉をもらってたんだ」と思えるような文章を意識すると◎です。
例えば、「100日を迎えた今、あなたの存在が家族の光です」とか、「どんな道を選んでも、あなたを信じています」。
少し詩的でも、気持ちが込められていればそれは“その子だけの物語”になります。
筆者の知り合いで、30歳の誕生日に祖母の手紙を読み返して涙したという方もいました。
“時間を超えるメッセージ”って、本当に存在するんですよね。
だからこそ、「今の気持ち」と「将来の応援」、その両方をそっと織り交ぜてみてください。
お食い初めで祖父母ができるサポートとは?


お食い初めで祖父母ができるサポートは何かについて解説します。
主役は赤ちゃんとパパママ。



でも祖父母だからこそできる“ちょっとした心遣い”が、場の雰囲気を和らげてくれるんです。
写真撮影や準備で活躍する
お食い初めの当日は、赤ちゃんにとっても家族にとっても「記念すべき一日」。
だからこそ、祖父母が“記録係”や“補助役”として動けると、すごく助かる存在になります。
例えば、スマホやカメラで家族写真を撮ってあげたり、料理や食器の準備を一緒に手伝うだけでも大きなサポート。
「ここで撮ると光がきれいだよ」とアドバイスするだけでも、場が和みます。
特にパパママは準備でバタバタしがちなので、「何かできることある?」のひと言が、ほんとに嬉しいんです。
祖父母として、静かに、でもしっかり支えてくれている…そんな存在がいるだけで、当日の安心感は全然違います。
食事中の声かけや盛り上げ役
赤ちゃんの前に“鯛”や“お赤飯”が並ぶ…でも、まだ食べられない…(笑)
そんな儀式を見守る時間こそ、祖父母の“和ませ力”が試される場面です。
「あら、もう大人みたいに座ってるね〜!」とか「歯がないのに鯛!?これは高級だぞ〜」など、ちょっとしたユーモアやツッコミで場を和ませてください。
赤ちゃんに語りかけたり、みんなで笑いながら儀式を楽しむことで、形式ばった雰囲気がやわらぎます。
お祝いって、「楽しいね」「嬉しいね」って言葉があるだけで、グッと記憶に残るものなんですよね。
パパママへのねぎらいの一言
お食い初めは、赤ちゃんの成長を祝う日…でも同時に、“ここまで育ててきた”パパママの努力をねぎらう日でもあります。
だからこそ、「よく頑張ったね」「ほんとにいいパパママだね」といった一言をぜひかけてあげてください。
生まれてから100日間、夜泣きや不安に悩んで、寝不足の日々を乗り越えてきた二人。
そんな日々を見てきた祖父母からのねぎらいは、言葉以上に大きな支えになります。
形式的じゃなくて、素直な感想でOK。「○○ちゃん、幸せそうな顔してるね」だけでも、すごく嬉しいんです。
メッセージを書くときも、赤ちゃんだけでなくパパママへの気遣いを一文入れてみてくださいね。
祖父母らしい距離感でサポート
一番大切なのは、やっぱり「祖父母らしい距離感」。
ついつい「あれやってあげたい」「もっとこうしたほうがいい」って口出ししたくなるけれど、そこはグッと我慢。
「何か必要なときはいつでも言ってね」と伝えて、あとは“見守るスタンス”でいるのがベスト。
必要とされれば自然と頼ってくれるし、そのときこそ力を発揮できる場面です。
祖父母は、“主役じゃないけど、欠かせない存在”。
その絶妙な立ち位置を楽しんで、あたたかい空気を作っていきましょう。
地域や家庭による違いと対応のコツ
地域や家庭による違いと対応のコツをご紹介します。
「うちはこうだった」が通じない場面もあるお祝い行事。



だからこそ、少しの“配慮”と“柔軟さ”が大きな信頼につながります。
地域ごとのお食い初めの習慣
実はお食い初めのやり方って、地域によってけっこう違うんです。
たとえば、関東では“祝い膳”に鯛・赤飯・煮物・香の物・お吸い物を並べるのが一般的ですが、関西ではお吸い物の具に「はまぐり」ではなく「しじみ」を使ったり、歯固めの石の大きさや置き方も違ったりします。
また、祖父母が「歯固めの石は神社から拾ってきたものを使うものだよ」と言っても、最近では「セットで買いました!」という家庭も多いです。
大切なのは、「違いを否定しない」こと。
「昔はこうだったけど、今はそれも素敵ね」と受け入れる姿勢があれば、家族みんなが気持ちよく過ごせます。
両家の文化の違いに配慮する
お祝いの席で意外と気を遣うのが、両家の文化や価値観の違い。
たとえば、片方の祖父母は「儀式をきっちりやるタイプ」で、もう一方は「形式より楽しく過ごせたらOK」派…なんてケース、珍しくありません。
祖父母としてはつい「こうしたほうが…」と言いたくなるけど、そこはグッと堪えるのが大人の役目です。
自分の思いを伝えるよりも、「場の調和を守る」ことを優先すると、結果的に信頼関係が深まります。
場の雰囲気をよく見て、片方に偏らないよう心がけましょう。
誰が主役かを意識する
お祝い事でつい忘れがちなのが、「主役は誰か」という視点。
お食い初めでは、もちろん赤ちゃんが主役。そして“今”育てているパパとママが、その大切なサポーターです。
祖父母が「自分が仕切らなきゃ」と前に出すぎると、場がぎくしゃくしてしまうことも。
「手伝えることがあれば言ってね」「すごく良い準備してくれたね」と、さりげなく寄り添う方が、感謝される存在になれます。



あくまで“陰の立役者”として、温かく見守るポジションが理想的ですね。
柔軟に対応して心地よい時間にする
大事なのは、100点の正解を目指すことじゃなくて、「気持ちよく過ごせる時間」を作ること。
赤ちゃんが泣いちゃっても、料理が少し遅れても、「大丈夫よ〜、赤ちゃんってそういうもんだよ」とニコッと笑ってくれる祖父母がいるだけで、場の空気はぐっと和らぎます。
予期せぬハプニングも「それも思い出」と受け止める余裕があると、パパママの心も軽くなります。
型にはまったお祝いよりも、“その家族に合った祝い方”を一緒に楽しめるのが、最高のサポートです。
将来読み返せるメッセージの残し方アイデア
将来読み返せるメッセージの残し方アイデアをご紹介します。



思い出は、“残し方”ひとつで一生ものになります。
あとで読み返したときに「あのときの気持ちがよみがえる」ような、素敵な残し方を選んでみましょう。
フォトブックにまとめる
お食い初めの写真と一緒に、メッセージを印刷して残せる「フォトブック」は大人気の方法です。
最近はスマホの写真アプリから簡単に作れるサービスも増えていて、コメントや日付、名前なども自由にレイアウト可能。
1ページに1言ずつ、祖父母の手紙を印刷するのも素敵ですよ。
アルバムとは違い“物語として綴れる”のがフォトブックの魅力。
将来、子どもが成長してから自分でページをめくる時間を想像すると、作る側も自然と気持ちがこもります。
ビデオメッセージとして残す
文字が苦手な方や、声で伝えたい想いがある方には「ビデオメッセージ」がおすすめ。
スマホひとつで撮れる時代だからこそ、ちょっと勇気を出して話してみましょう。
「○○ちゃん、100日おめでとう。おじいちゃんもおばあちゃんも、あなたのことが大好きだよ。」
そんな短い言葉でも、表情や声のトーンが加わるだけで、ぐっと感情が伝わります。
成長したあとに見返したら、“声を聞いて涙が出た”なんてこともあるはずです。
動画ならではの臨場感が、“時を超えるメッセージ”になりますよ。
デジタルアルバムで共有する
家族LINEやクラウドアルバムなど、デジタルで共有できる場所にメッセージを保存しておく方法もあります。
例えば、赤ちゃんの写真と一緒に「このときはこんなことを思っていたよ」とコメントを残したり。
Googleフォトやみてねなどのアプリでは、写真にコメントを書き込める機能があるので、祖父母からの言葉を写真と一緒に記録できます。
スマホ世代のパパママにとっては、手軽に読めて、いつでも見返せる点が嬉しいポイント。
リアルな形にこだわらなくても、心に届く「記録のかたち」はたくさんあります。
手書きの味わいを活かす
デジタル全盛の時代だからこそ、「手書き」の温かみは特別です。
たとえ字が崩れていても、文字の強弱や筆圧から、そのときの感情が感じられることもありますよね。
便せんに一筆書くだけでもいいですし、色紙やミニ絵本に書き込んで“世界に一つだけのメッセージ集”にするのもおすすめ。
スタンプを押したり、ちょっとしたイラストを添えるだけで、ぐっと個性が出ます。
子どもが大きくなったときに、「これはおばあちゃんが手で書いてくれたんだよ」と語れる記録は、思い出の中でも特別なものになるでしょう。
祖父母から贈るお食い初めのお祝いメッセージまとめ


- お食い初めのメッセージは、祖父母の「愛情」と「応援の気持ち」を素直に込めることが大切です。
- フォーマルからカジュアル、ユーモアたっぷりのものまで、家庭の雰囲気に合った文体を選ぶと◎。
- メッセージに家族のつながりや、赤ちゃんへの未来への願いを加えると、より深く響きます。
- お祝いの言葉は手紙、カード、SNS、プレゼント添えなど、伝え方次第で印象が大きく変わります。
- ネガティブな表現や一方的な価値観の押しつけは避け、思いやりのある言葉選びを心がけましょう。
- 写真や動画、手書きカードなど、記録として“残せる形”にすることで、将来の宝物になります。
- 何よりも、「自分らしい言葉」で語りかけることが、いちばん心に届くメッセージになりますよ。
お祝いの言葉って、形式じゃなく“気持ち”なんですよね。
赤ちゃんの健やかな成長を願うその想い、誰よりも強く感じているのは、きっと祖父母であるあなたです。
だからこそ、言葉がうまくまとまらなくても大丈夫。
大切なのは、あなたのまなざしや経験、日々湧いてくる優しさをそのまま文章に込めること。



この記事では、そんな想いを言葉にするためのヒントをたくさんご紹介しました。
読みながら「あ、この表現なら自分にもできそう」と思えたなら、それがきっとあなたらしいメッセージのカタチです。
どうか、背伸びせず、飾らず、心からのひと言を贈ってみてくださいね。
その言葉は、きっとお孫さんとご家族の心に、あたたかく残り続けるはずです。