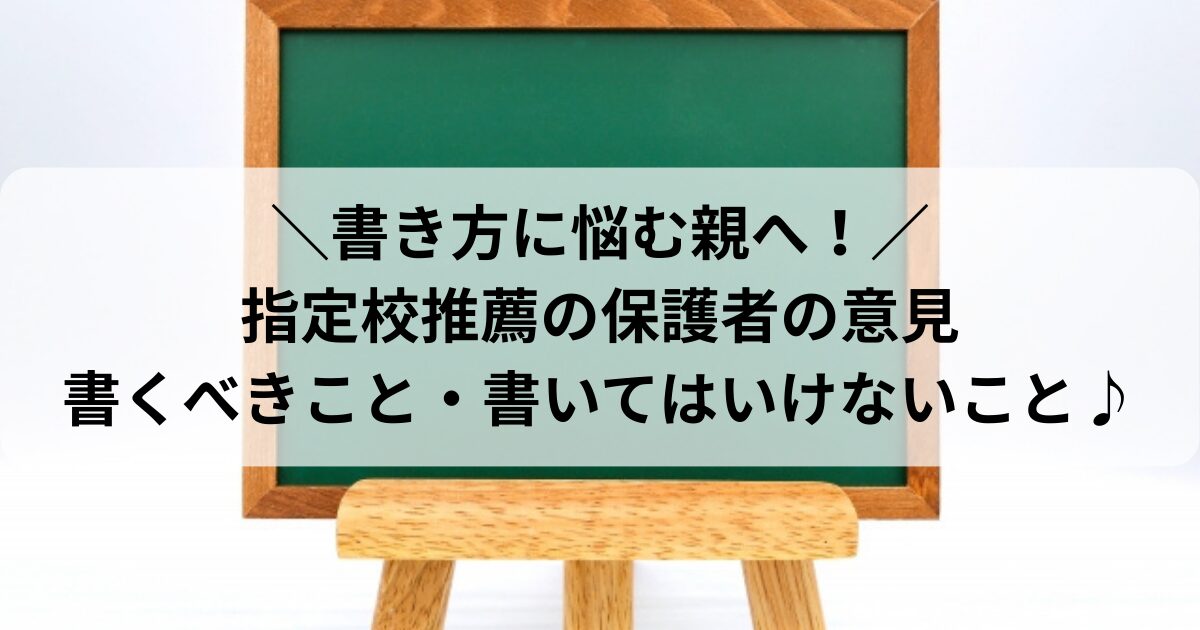指定校推薦の校内選考書類にある「保護者の意見」欄。
いざ書こうとすると「何を書けばいいの?」「合否に影響するの?」と迷う親御さんも多いですよね。
結論から言うと、保護者の意見は合否を左右する決定要素ではありません。
ただし、子どもの希望を後押しする大切な推薦文としての役割があります。
本記事では、指定校推薦における保護者の意見の基本的な書き方や注意点、さらに就職希望・大学院進学希望・将来未定などシーン別の例文までまとめました。
これを読めば、親として何を書けばよいか迷わず、安心して書類を完成させられます。

お子さんの努力を応援する気持ちを、シンプルかつ前向きに伝えることがポイントですよ!
指定校推薦の保護者の意見の例文集(シーン別)
ここでは、指定校推薦の校内選考書類に書く「保護者の意見」を、具体的なシーンごとにまとめました。
親の立場から子どもをどう後押しすればよいかをイメージできるように、複数のパターン別に例文を紹介しますね。
例文を参考にしながら、自分のお子さんに合わせてアレンジしていくことが大切です。
将来の就職を見据えた場合
子どもが将来の就職を強く意識している場合、大学での学びと就職先のつながりを意識して書くのがおすすめです。
以下の表にポイントを整理しました。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 学びと就職の関連 | 「○○大学△△学部で学ぶ内容が、□□業界で必要とされる知識につながっている」 |
| 努力や取り組み | 「高校生活では欠席も少なく、家庭学習や課題に積極的に取り組んできた」 |
【例文1】
本人は□□業界での将来を見据え、その基盤となる学びを得るため、○○大学△△学部を強く志望しております。
大学説明会や資料から得た情報を真剣に受け止め、自身の進路に直結する学びがそこにあると確信し、強い希望を持つに至りました。
家庭においても、日々の学習に真摯に向き合い、自ら課題を探して取り組む姿勢を継続しております。
こうした努力を重ねる姿を身近で見てきたことから、進学後も学びを深め、将来の目標に向けて成長を続けていけると信じております。
保護者といたしましても、その意志を尊重し、最大限の後押しをしていく所存です。
【例文2】
本人は将来□□業界で働きたいという夢を持ち、そのために必要な学びを得られる場として○○大学△△学部を志望しております。
説明会や資料を通じて本人が感じ取った魅力を、日常の会話の中で何度も話してくれる姿から、この大学で学びたい気持ちが強く伝わってまいりました。
家庭でも、時間を見つけては机に向かい、小さな努力を積み重ねている姿を日々目にしております。
その前向きな姿勢を大切にしながら、進学後も自分らしく学びを深めていけると信じております。
親としても、その気持ちを尊重し、温かく見守りながら支えてまいりたいと考えております。
大学院進学を目指している場合
大学での学びをさらに発展させたいと考えている子どもには、「継続性」と「探究心」を強調するとよいでしょう。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 興味の継続 | 「小学生のころから理科に興味を持ち続け、現在もその探究を続けている」 |
| 学びの深化 | 「学部での学びを基盤として、大学院でさらに専門性を高めたいと考えている」 |
【例文3】
本人は幼いころから××に深い興味を持ち、その関心を持続させながら学習に励んでまいりました。
その姿勢は高校生活においても変わらず、授業や自主学習を通じて知識を広げ、理解を深めようと努めております。
本人が志望する○○大学は、当該分野を専門的かつ体系的に学べる環境が整い、さらに大学院進学を目指す学生への支援体制も充実していると知り、強い意志をもって志望を決定いたしました。
家庭でもその意欲的な姿勢を日々感じており、進学後も継続的に努力を重ね、さらなる成長を遂げていくものと確信しております。
保護者といたしましても、その歩みを全力で後押ししてまいります。
【例文4】
本人は幼いころから××に関心を持ち続け、その気持ちは年を重ねるごとにより深まってまいりました。
日常の学びや活動の中でも、その興味を大切にしながら探究を続けている姿が見受けられます。
本人が第一志望とする○○大学は、その分野を幅広くかつ体系的に学ぶことができ、大学院進学を目指す環境も整っていると知り、自然と進学への思いを強くしたようです。
家庭でも日々学習に前向きに取り組む様子を目にし、その努力を尊重しながら見守っております。
進学後も自分らしく学びを深められるよう、親としても温かく支えていきたいと考えております。
将来がまだ定まっていない場合
子どもが具体的な将来像を描けていない場合でも、「幅広く学べる環境」と「本人の前向きな姿勢」を強調すれば安心感を与えられます。
具体的な進路が決まっていなくても、学ぶ姿勢を肯定的に書くことが重要です。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 幅広い学び | 「○○大学では多様な分野を学べるため、将来を考えるきっかけになる」 |
| 前向きな姿勢 | 「現在はスポーツや芸術に励みながら、進学後にやりたいことを探している」 |
【例文5】
本人はまだ具体的な将来像を定めてはいないものの、○○大学における多様な分野の学びに触れることで、自分の適性を見極め、進路を形づくっていきたいと強く希望しております。
これまでの学校生活では、授業や家庭学習に積極的に取り組み、また部活動にも誠実な姿勢で向き合い、仲間と共に努力を重ねてまいりました。
そのような姿勢は、未知の分野に挑戦する際にも大きな支えとなるものと考えております。
保護者といたしましても、本人が多様な経験を通じて自らの将来を見出していけるよう、温かく後押ししてまいります。
【例文6】
本人は進学後の進路をまだ模索している段階ですが、○○大学で幅広い分野に触れることで、自分の将来を考える大切なきっかけを得たいと語っております。
日々の学校生活では、授業や家庭学習に意欲的に取り組むとともに、部活動にも積極的に励み、仲間との協力を大切にしてきました。
その前向きな姿勢を、私たち家族も心強く感じております。
まだ具体的な道が決まっていなくても、その姿勢こそが将来につながる大切な力になると信じております。
親としても、本人の歩みを温かく見守りながら、これからの挑戦を支えてまいりたいと考えております。
学業面を中心にした例文の場合
学業を軸に子どもの努力や成果を記入する場合、成績や学習態度を具体的に書くと説得力が増します。
「得意科目」や「努力の過程」を盛り込みましょう。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 成績や得意分野 | 「数学や理科が得意で、理系の学部に適性がある」 |
| 学習への姿勢 | 「毎日コツコツと自宅学習に取り組んできた」 |
【例文7】
本人は高校生活を通して日々の学習に真剣に向き合い、基礎を大切にしながら理解を深めてまいりました。
特に理数系科目においては持ち前の探究心と粘り強さを発揮し、得意分野として着実に成果を上げております。
志望する○○大学△△学部では、これまで培ってきた力をさらに伸ばすことができると確信しており、本人も高い意欲を持っております。
その姿勢を日々見守る中で、進学後も積極的に学び続け、目標に向かって努力を重ねていけると強く感じております。
保護者といたしましても、その歩みを尊重し、力強く支えてまいりたいと考えております。
【例文8】
本人は高校生活を通して学習に真摯に向き合い、特に国語や英語などの文系科目に強みを持っております。
読解や表現に関わる課題にも楽しみながら取り組み、自ら考えを深めていく姿が印象的でした。
志望する○○大学△△学部では、その得意分野をさらに広げ、多様な学びを通じて新しい視点を培うことができると感じております。
進学に向けて日々努力を続ける様子から、学びへの意欲と粘り強さを実感しております。
親としても、その歩みを尊重し、これからも温かく支え続けていきたいと考えております。
人物像や人柄を強調した例文の場合
学力以外にも、誠実さや協調性などの人柄を伝えるのも効果的です。
学校や家庭での様子をエピソードとして盛り込むと、読み手に伝わりやすくなります。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 誠実さ | 「約束を守り、責任感を持って行動している」 |
| 協調性 | 「クラスメイトや後輩からも信頼されている」 |
【例文9】
本人は誠実な人柄をもとに、周囲から自然と信頼を得てきました。
学級活動などでは責任を持って役割を果たし、仲間の意見をよく聞きながらまとめていく姿が印象的でした。
自ら前に立つというよりは、相手を尊重しながら雰囲気を整え、結果的に全体を導いていく姿勢に、温かなリーダーシップが感じられます。
こうした姿勢は、新しい環境においても人との協働を支え、学びをより深める力になると考えております。
保護者といたしましても、その誠実さと人を思いやる心を尊重し、これからの歩みを見守り続けたいと願っております。
【例文10】
本人はこれまでの学校生活において、常に誠実な態度で物事に向き合い、相手を思いやる姿勢を大切にしてまいりました。
友人や周囲との関わりにおいては、相手の立場に立って考え、助け合う姿が自然に見られ、その温かな人柄が信頼につながっていると感じております。
学級活動などでも責任感を持って役割を果たし、周囲と協調しながら進めることで、円滑な雰囲気づくりにも貢献しておりました。
こうした誠実さや思いやりの心は、大学での学びや新たな環境においても必ず活かされるものと確信しております。
親としても、この姿勢を尊重し、これからの成長を温かく見守ってまいりたいと考えております。
部活動や課外活動を取り入れた例文の場合
部活動や課外活動に打ち込んできた姿を記入するのも良い方法です。
努力や成果、活動から得た経験を大学での学びに結びつけましょう。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 活動実績 | 「部活動で最後まで継続し、努力を続けてきた」 |
| 得た経験 | 「挑戦する姿勢やリーダーシップを身につけた」 |
【例文11】
本人は高校3年間、○○部に所属し、日々の練習に真剣に取り組む中で努力と忍耐力を身につけてまいりました。
大会での成果はもちろん、困難な状況にあっても仲間と声を掛け合い、協力して目標を達成する姿勢は大きな成長の証と感じております。
こうして培った粘り強さや協調性は、学業や将来の進路を歩む上で必ず役立つものと信じております。
志望する○○大学においても、この経験を基盤にさらなる学びを深めていけると確信しております。
保護者といたしましても、その姿勢を尊重し、これからも支えてまいりたいと考えております。
【例文12】
本人は高校3年間、○○部に所属し、日々の活動を通じて粘り強く取り組む姿勢を大切にしてまいりました。
練習や大会では成果だけでなく、仲間と共に励まし合いながら前進することで、協力の大切さや人とのつながりの温かさを学んできたように感じます。
その過程で身につけた前向きな姿勢は、大学での学びに対しても必ず役立つと信じております。
志望する○○大学に進学してからも、これまでの経験を糧に、自らの可能性を広げていってほしいと願っております。
保護者といたしましても、本人が自らの力を伸ばしていけるよう、陰ながら応援してまいります。
将来の目標や進路希望を盛り込んだ例文の場合
将来の夢やキャリアにつながる内容を記入すると、子どものモチベーションを伝えられます。
大学での学びと進路の一貫性を示すのがポイントです。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 将来の夢 | 「保育士になりたい」「研究職を目指している」 |
| 大学との関係 | 「○○大学△△学部での学びが夢の実現に直結する」 |
【例文13】
本人は将来□□の分野で社会に貢献できる仕事に就きたいという明確な目標を持ち、その基盤を築く場として○○大学△△学部を強く志望しております。
大学説明会に参加した際にも、その学びの内容や環境に強く惹かれ、ここで学びたいという強い意志を抱いた様子が印象的でした。
これまでの学習姿勢からも、進学後に着実に努力を続けていけるものと確信しております。
保護者といたしましても、本人の将来に向けた歩みを信じ、力強く後押ししてまいりたいと考えております。
【例文14】
本人は将来□□の分野で働くことを目標に掲げ、その基礎をしっかりと学べる場として○○大学△△学部を志望しております。
説明会での話を聞いた際には、自分の夢に直結する学びがここにあると感じ、ますます進学への思いを強めておりました。
日常の中でも学習に前向きに取り組み、少しずつ努力を積み重ねる姿を親としても頼もしく感じています。
これからもその気持ちを大切にしながら、自分の歩みを進めていけるよう、そっと寄り添ってまいりたいと考えております。
家庭での様子を交えた例文の場合
家庭での学習習慣や日常の姿を交えると、親にしか書けない「オリジナルな視点」を加えることができます。
日頃の努力や態度を具体的に書きましょう。
| 書き方の視点 | 具体例 |
|---|---|
| 家庭での学習 | 「毎日決まった時間に机に向かっている」 |
| 生活態度 | 「家事を手伝いながらも学習を両立している」 |
【例文15】
本人は日常生活においても自らを律し、毎日欠かさず学習を続けております。
学業への取り組みに加え、家庭では家事や手伝いを積極的に担い、責任感を持って行動する姿が日々見られます。
そのような規律ある生活と真面目な姿勢は、大学での学びや新たな生活環境の中でも必ず活かされるものと考えております。
保護者といたしましても、こうした努力を信じ、将来に向けて着実に歩みを進めていけるよう全力で支えてまいりたいと存じます。
【例文16】
本人は規則正しい生活を心がけながら、学習を日課として継続してまいりました。
家事や家庭の役割にも積極的に関わることで、家族の一員としての責任を学び、少しずつ成長してきた姿を感じております。
この日常の積み重ねは大学での学びにも必ず結びつき、自らを律して前に進む力になると考えております。
保護者といたしましても、これまでの姿勢を信じ、新たな環境でも実りを得られるよう願っております。
指定校推薦で求められる保護者の意見とは?



まずは「保護者の意見」がどんな役割を持つのかを整理しておきましょう。
指定校推薦においては、生徒本人の学業成績や学校での活動が最も重視されますが、保護者の意見も補足的な情報として提出されることがあります。
合否を決める直接の要素ではありませんが、子どもを支える姿勢を示す大切な欄です。
校内選考書類の中での役割
保護者の意見欄は、主に「家庭からの後押し」として記入するものです。
学校側は、家庭が進学にどのように関与しているか、そして子どもをどのように理解しているかを知ることができます。
| 役割 | 具体例 |
|---|---|
| 後押しの確認 | 「親としても子どもの意思を尊重し、進学を応援したい」 |
| 子どもの理解 | 「小さいころから理科に興味を持ち、今も継続して学んでいる」 |
合否にどこまで影響するのか
実際のところ、保護者の意見そのものが合否を左右することはほとんどありません。
しかし、推薦書類として提出される以上、内容が極端に否定的だったり、子どもの意見と矛盾しているとマイナスの印象を与える可能性があります。
つまり「合否には直結しないが、推薦を後押しする文書」としての役割を意識すべきなのです。
保護者の意見に書くべき基本のポイント



次に、保護者が実際に意見を書く際の基本的なポイントを整理します。
ここを押さえておけば、どんなケースでも安心してまとめられます。
「子どもの適性」「志望理由」「将来の目標」の3つが基本軸です。
子どもの大学適性について
大学や学科と子どもの適性を結びつける書き方を意識しましょう。
例えば「得意科目と学部の方向性が一致している」「興味分野とカリキュラムが合っている」など、納得感のある表現が好まれます。
| 観点 | 記入例 |
|---|---|
| 学力や科目の適性 | 「数学が得意で、理系学部の学習に向いている」 |
| 興味や活動の延長 | 「高校で研究してきたテーマを大学でさらに深めたい」 |
志望理由をどう親の立場から表現するか
子ども本人が話している志望理由を補足し、親としての理解や共感を添えるのが理想です。
「将来の夢を語ってくれた」「説明会で強い意欲を持った」など、親だからこそ伝えられる背景を盛り込みましょう。
将来の目標と親の後押し
最後に、将来の目標を親の立場から後押しする表現で締めくくると文章が引き締まります。
たとえ子どもの目標がまだ漠然としていても、「本人の前向きな姿勢を尊重する」という書き方で十分です。
重要なのは、子どもを信じて支える気持ちが伝わることです。
指定校推薦で避けるべきNGな書き方
保護者の意見を書くときに「やってはいけないこと」もあります。
せっかくの推薦文が逆効果にならないように、注意点を確認しておきましょう。



NG例を知っておくことで、安心して前向きな文章が書けますからね!
否定的な意見や反対姿勢はNG
「学費が不安だから反対」「本人の意欲が足りないと思う」といった否定的な内容は避けるべきです。
保護者の意見欄は、子どもの進学を後押しするために存在しています。
| NG表現 | 改善例 |
|---|---|
| 「まだ考えが甘いので反対している」 | 「進学を通じて考えを成熟させていってほしいと願っている」 |
| 「学費の面で厳しい」 | 「家族で支えていきたいと考えている」 |
反対や否定ではなく、応援のスタンスを示すことが大切です。
長すぎる文章・抽象的な言葉に注意
推薦書類はあくまで補足ですので、長文になりすぎないようにしましょう。
また「頑張っている」「良い子だと思う」といった抽象的な表現よりも、具体的なエピソードを添えると説得力が増します。
例:
- 抽象的:「部活動を頑張っています」
- 具体的:「3年間サッカー部に所属し、レギュラーとして最後まで練習に励んできました」
志望理由のサポートの仕方
子ども本人の志望理由はもちろん重要ですが、保護者としてもサポートできる部分があります。
ここでは、子どもの考えを引き出し、推薦書類に反映させるための方法を紹介します。
「一緒に考える」姿勢が、自然で前向きな文章を生み出します。
子どもとの話し合いで引き出すポイント
まずは「なぜその大学なのか」「学部でどんなことをしたいのか」を子どもに問いかけてみましょう。
本人の言葉をメモに残しておくと、意見欄を書く際に参考になります。
| 質問例 | 意見に活かせる形 |
|---|---|
| 「説明会で印象に残ったことは?」 | 「大学説明会で××を聞き、より志望意欲が高まったと話していた」 |
| 「将来どんなことをしたい?」 | 「将来□□の仕事を目指しており、その基盤をこの大学で築きたいと言っている」 |
オープンキャンパスや資料を活用する方法
オープンキャンパスやパンフレット、大学の公式サイトなどから得た情報を、親子で共有するのも効果的です。
「本人が実際に見て感じたこと」を具体的に記録しておくと、意見欄に説得力を持たせられます。
体験や資料に基づいた具体性のある表現は、文章に厚みを加えてくれます。
校内選考での保護者の意見と実際の影響
ここまで具体的な書き方を見てきましたが、実際のところ「保護者の意見」はどの程度影響があるのでしょうか。
結論から言えば、直接的に合否を左右するものではありません。
ただし、推薦書としての役割を持つ以上、適切な姿勢を示すことが大切です。
選考に影響しない部分
保護者の意見は、本人の成績や活動実績と比べると評価対象にはなりません。
学校側は「親も進学を理解しているか」を確認する程度の位置づけです。
| 影響しない要素 | 理由 |
|---|---|
| 文章の巧拙 | 合否は学力や活動で判断されるため |
| 親の学歴・職業 | 本人の能力や適性とは無関係だから |
推薦文として意識すべき姿勢
影響が少ないからといって、適当に書いてしまうのは避けたいところです。
あくまで「推薦文」という性格を持っているため、子どもの希望を後押しする形でまとめましょう。
否定的な言葉は避け、簡潔かつ前向きな表現を心がけることが重要です。
指定校推薦の「保護者の意見」例文まとめ





最後に、指定校推薦の保護者の意見で意識すべきことを整理しますね!
書き方のテクニックはいろいろありますが、最も大切なのは「親が子どもを応援している」というメッセージを伝えることです。
前向きな姿勢をシンプルに示すだけで十分に良い推薦文になります。
子どもを後押しする姿勢を伝える
「志望校で学ぶことを応援したい」「本人の努力を信じている」という姿勢を示すことが、最も大切です。
文章の長さや表現に悩んでも、応援の気持ちがあれば自然と伝わります。
シンプルかつ前向きな文章を心がける
細かい装飾よりも、短く端的にまとめるほうが読みやすく伝わりやすいです。
最後は「親として尊重し、見守りたいと思います」と締めるのが無難で安心です。
| 悪い例 | 良い例 |
|---|---|
| 「まだ将来が決まっておらず心配です」 | 「進学先で学びながら将来を見つけてほしいと応援しています」 |
| 「本人に任せています」 | 「本人の希望を尊重し、家庭としても支えたいと考えています」 |